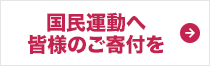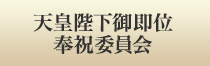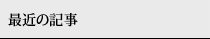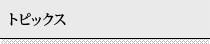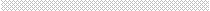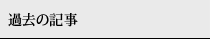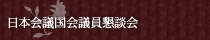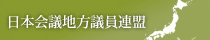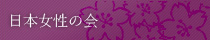戦後政治の原点としての[東京裁判]批判
独立国家日本の「もう一つの戦後史」
終戦50周年国民委員会 ※佐藤和男・青山学院大学名誉教授監修『世界がさばく東京裁判』(明成社)「第6章」より転載。
「文明の裁き」と称して鳴り物入りで始められた東京裁判は実に2年6カ月もの時間を費やし、開廷423回、総計費27億円をかけて1948年(昭和23年)11月に判決を下した。我が国の指導者7人に絞首刑を宣告したこの判決は、これまでに紹介したように、弁護団ばかりでなく、少数意見を提出した判事たちや連合国の政治家たちからも厳しい批判を浴びた。
いくら国際法に基づいた公正な裁判だったと宣伝しても、真実は隠せない。「いかさまな法手続き」で行なわれた「政治権力の道具」に過ぎなかった東京裁判を強行したことで、GHQ(占領軍総司令部)及びアメリカ政府の権威は低下することとなった。判決が出された翌年の1949年(昭和24年)1月11日、アメリカのワシントン・ポスト紙は論説に次のように記した。
《米国の声望はもとより、正義の声望までも……東京において危うくされたことが、次第に明白になりつつある。》(『勝者の裁き』p.187.)
GHQは東條元首相らを処刑した1948年(昭和23年)12月23日の翌日、準A級戦犯容疑者19名を一度も裁判にかけることなく巣鴨拘置所からそそくさと解放し、以後、法廷は二度と開かれることはなかった。なお、連合国極東委員会は翌1949年2月24日、「国際軍事裁判はこれ以上行なわない」と決定した。
この東京裁判を、戦後独立を果たした我が国の政治家及び国民が、どのように受け止めてきたかについては、ほとんど知られていない。このため、我が国は「東京裁判」を受け入れることで国際社会に復帰したという誤解が流布されてしまっている。しかし、真実はそうではなかった。
そこで、独立国家として東京裁判を正面から批判してきた「もう一つの戦後史」を、ここに紹介したい。
■講和会議で東京裁判を批判したメキシコ大使
国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって戦争が正式に終結するものとされる。それまでは法的には「戦争状態」の継続と見なされるので、いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判や、アジア太平洋の各地で開廷されたB・C級戦犯裁判も、連合国軍による軍事行動(戦争行為)の一種と理解されている。しかし、軍事行動は講和条約の発効と共に終結する。
つまり、昭和27年(1952年)4月28日のサンフランシスコ対日講和条約の発効とともに、国際法的には日本と連合国の間に継続していた「戦争状態」は終焉し、独立を回復した日本政府は、講和に伴う「国際法上の大赦」を規定する国際慣習法に従って、戦争裁判判決の失効を確認した上で、連合国が戦犯として拘禁していた人々をすべて釈放することができたはずなのである。
ところが、そうはならなかった。
そもそもこの講和条約を起草したのはサンフランシスコ講和会議であるが、この会議で署名された条約草案は、アメリカ、イギリス、日本の3カ国間交渉で起草され、最終案文は、会議の始まる僅か1カ月前に発表され、それ以外の49の参加国は、基本的にはそれを承認するために招請されたわけである。その講和条約第11条には、
《日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。……極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限[赦免し、減刑し、及び仮出獄させる]は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。》
と規定されていた。
本来ならば、日本政府は講和条約の発効とともに、戦犯として拘禁されていた者を釈放していいはずだが、「(アメリカの)審判と慈悲に絶対的に従う」政権の樹立を目的として東京裁判を含む占領政策を遂行してきたアメリカは、講和独立後も、アメリカの「審判」に従った刑の執行を日本政府に要求したのである。
1951年(昭和26年)9月5日、サンフランシスコ講和会議が開かれた。この会議で、スリランカ代表のJ・R・ジャヤワルダナ蔵相(のち首相、大統領)が「私は、前大戦中のいろいろな出来事を思い出せるが、当時、アジア共栄のスローガンは、従属諸民族に強く訴えるものがあり、ビルマ、インド、インドネシアの指導者たちの中には、最愛の祖国が解放されることを希望して、日本に協力した者がいたのである」として、日本の独立回復を強く支持する格調高い演説をしたことは有名である。
この会議の席で、日本に対して懲罰的な講和条約第11条がやはり問題となった。ラファエル・デ・ラ・コリナ駐米メキシコ大使はメキシコ代表として
《われわれは、できることなら、本条項[講和条約第11条]が、連合国の戦争犯罪裁判の結果を正当化しつづけることを避けたかった。あの裁判の結果は、法の諸原則と必ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なしという近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信ずる。》(『各法領域における戦後改革』p.89.)
と発言、アルゼンチン代表のイポリト・ヘスス・パス駐米アルゼンチン大使も
《わが政府は、日本国民に彼等の主権を回復させるこの条約に賛意を表せざるを得ないのであります。……この文書の条文は、大体において受諾し得るものではありますが、2、3の点に関し、わが代表団がいかなる解釈をもつて調印するかという点、及びこの事が議事録に記載される事を要求する旨を明確に述べたいのであります。……本条約第11条に述べられた法廷[東京裁判]に関しては、わが国の憲法は、何人といえども正当な法律上の手続きをふまずに処罰されない事を規定しています。》(外務省編『サン・フランシスコ会議議事録』p.299.)
と語り、「正当な法手続きを踏まずに日本人指導者を処罰した東京裁判は、アルゼンチン憲法の精神に反している」として、東京裁判を間接的に批判したのである。しかし、メキシコ、アルゼンチン両代表の発言は記録にとどめられただけで、条約草案はそのまま条約本文となった。
■4000万人を越えた「戦犯」釈放署名
かくして1951年(昭和26年)9月8日、サンフランシスコにおいて日本を含む416カ国が対日講和条約に調印し、翌1952年(昭和27年)4月 28日に発効。日本は晴れて独立を回復したが、講和条約第十一条に、関係国の同意なくして日本政府は勝手に戦争受刑者(戦犯)を釈放してはならないと規定されていたため、講和条約の恩恵を受けることなく、巣鴨、モンテンルパ(フィリピン)、マヌス島(オーストラリア)で引き続き1224名もの日本人および戦時中日本国籍を有していた朝鮮人・台湾人がA級及びB・C級戦犯として服役しなければならなかった。
それを知った国民は驚いた。講和条約が発効したのに何故敵国に裁かれた同胞たちは釈放されないのか。連合国が戦時の軍事行動の一環として行なった戦争裁判の効力は失われ、戦争受刑者も全員釈放されるのが国際慣例ではなかったのか―。そのような疑問から、戦争裁判に対する国民の関心は一気に高まった。
実は、朝鮮戦争の勃発に伴いアメリカの対日政策が変更されたため、軍事占領も後期になると日本国民の言論の自由もかなり容認されるようになり、占領中の昭和 25年(1950年)4月、「国づくりは戦争の後始末から」を合言葉に引揚問題や戦争受刑者問題に取り組んできた「日本健青会」のメンバーが中心となって「海外抑留同胞救出国民運動」(総本部長は衆議院議長)が発足し、戦争受刑者釈放運動が取り組まれていた。
このため講和条約発効後の1952年(昭和27年)6月5日から全国一斉に「戦争受刑者の助命、減刑、内地送還嘆願」の署名運動が始められるや、戦争受刑者釈放運動は大いに盛り上がった。その様子を国学院大学の大原康男教授は次のように紹介している。
《まず日本弁護士連合会が口火を切り、27年6月7日「戦犯の赦免勧告に関する意見書」を政府に伝えた。これがきっかけとなって、戦犯釈放運動は瞬またたく間に全国的規模の一大国民運動となり、早くからこの運動に取り組んで来た日本健青会を始めとする各種団体や地方自治体は、政府は平和条約第11条に基づいて関係各国に対して赦免勧告を行なうよう続々と要請した。
署名運動も急速に広がり、共同通信の小沢武二記者の調査によれば、地方自治体によるもの約2000万、各種団体によるもの約2000千万、合計約4000万に達し、また各国代表部や国会・政府・政党などに対する陳情も夥おびただしい数にのぼっている。》(「“A級戦犯”はなぜ合祀されたか」p.112~113.、『靖国論集』)
こうした国民世論の後押しを受けて、政府は直ちに国内で服役中の戦犯の仮釈放および諸外国で服役中の戦犯を我が国に送還する措置について関係各国と折衝を開始した。7月11 日の閣議では、岡崎勝男外相が中心となって今後一層関係国の了解を求めるよう努力することを申し合わせた。七月下旬、政府の肝入りで日本健青会の末次一郎氏(現、安全保障問題研究会、新樹会代表)が訪米し、トルーマン大統領に戦争受刑者の釈放について次のような要請書を提出した。
《私は祖国日本の完全なる独立と真実の世界平和とを希求する青年の立場から、今次戦争における戦争犯罪人として今猶獄舎にある人々の全面的釈放の問題について、我々の強い要請を披瀝するものである。
今次戦争における所謂、戦争犯罪処断の目的は、1つには人類の世界から戦争を消滅させようとする人間の善意の祈りであろうが、然し1つには勝者の敗者に対する徴罰の1つの形式であったと思う。
従ってこの所謂、政治目的を背後に蔵した戦争裁判の結果は、或は全く無実の人々を多数苛酷な罪名の下に拘束し、或は裁判の行われたる時期によって罪の軽重甚だしく、或は文明と人道の名の下に敗者のみが一方的に裁かれるという数々の不当な事実が発生して来たのである。
この様な重大な問題が、講和条約におけるとりきめが甚だしく不備であったために、条約発効後数ケ月を閲けみしたる今日、猶未解決の儘まま放置されて居り、かえって連合軍占領期間中行われて居た仮出所の制度すらも、日本の管理に移されると共に之が停止を命ぜられるという逆現象さえ呈しているのである。このことは、講和成立と同時に戦争犯罪を全面解決した歴史上の先例から考えても、又上述した如き今次裁判の極めて特異な性格から見ても、講和成立と同時に当然全面釈放が行われるものと期待した我々日本国民に、甚しい失望と不満を与え、殊に無実の罪に拘束されている多くの人々に激しい憤りをさえ持たせるに至って居る。アメリカの良識を代表される閣下が、もしも現在巣鴨に拘置中の米国関係者427名に対して、全面釈放の措置を断行されるとすれば、我々日本人が最も心を痛めている、比島の死刑囚59名の助命、並びに同島にある111名の拘置者及び濠洲[オーストラリア]マヌス島にある206名の日本人の内地送還についても、必ず喜ぶべき結果が齎もたらされるであろうと確信する。
我々は、この戦争裁判の背後にある政治目的は完全に達せられたと確信するが故に、且又この現状が日米両国民の親善を阻害するのみならず、共産主義者たちに逆用の口実を与えることを虞おそれるが故に、猶又この問題は講和発効と同時に解決されるのが至当であって、個別審査によって事務的に減刑等を行なうという如き姑こ息そくなる手段によって解決すべきでないと信ずるが故に、更に日本国民は、この解決によって始めて真に平和的国家の建設に邁進し得ると確信するが故に、閣下が、米国関係の全戦犯者に対する即時釈放を断行されんことを、茲ここに強く要請するものである。》(末次一郎『「戦後」への挑戦』p.151~153.)
■「戦犯」釈放に立ち上がった日本政府
こうした世論の盛り上がりの中で、政府の対応は素早く、まず巣鴨在所者の処理について関係国の許容を得る可能性の多い仮出所の勧告を行う方針のもとに、昭和27年(1952年)8月11日までに232名の仮出所の勧告を行い、8月15日、今度は巣鴨刑務所に服役中のB・C級戦犯全員八百十九名の赦免を関係各国に要請する勧告を行なった。8月19日には新木駐米大使がアリソン米国務次官補を訪問し、B・C級日本人戦犯釈放問題で再びアメリカ政府の好意的配慮を要請。10月11日には、立太子礼を機会に、国内および海外に抑留されているA級を含む全戦犯の赦免・減刑を関係各国に要請したのである。
度重なる日本政府の要請に11月13日、アメリカ政府はワシントンの日本大使館に対して極東国際軍事裁判所で裁判を受けたA級戦犯に関する赦免、減刑、仮出所などの処置を協議するため、同軍事裁判に参加した連合国との間に近く話し合いを始める考えであることを通告した。
そこで、日本政府の後押しをすべく11月27日、自由党(吉田茂総裁)は総務会で、他国に抑留中の戦犯死刑囚の助命、有期刑者の内地送還ならびに内地抑留中の戦犯の釈放に関する決議案を今国会に提出することを決定し、12月9日、第十五回国会・衆議院において田子一民議員ほか58名提出、自由党、改進党(重光葵総裁)、左右両派社会党、無所属倶楽部の共同提案による、次のような「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」が圧倒的多数で可決されたのである(労農党のみ反対)。
《独立後すでに半歳、しかも戦争による受刑者として内外に拘禁中の者はなお相当の数に上り、国民の感情に堪え難いものがあり、国際友好の上より遺憾とするところである。
よつて衆議院は、国民の期待に副い家族縁者の悲願を察し、フイリツピンにおいて死刑の宣告を受けた者の助命、同国及びオーストラリア等海外において拘禁中の者の内地送還について関係国の諒解を得るとともに、内地において拘禁中の者の赦免、減刑及び仮出獄の実施を促進するため、まずB級及びC級の戦争犯罪による受刑者に関し政府の適切且つ急速な措置を要望する。
右決議する。》(「官報号外」昭和27年12月9日)
この国会決議が東京裁判を否定する意図をもって行なわれたことは、この提案の趣旨説明に立った田子一民議員の次の趣旨説明で明らかだ。
《…… わが国は、平和条約の締結によつて独立国となつて、すでに半歳以上をけみしておるのであります。国民の大多数は、独立の喜びの中に、新生日本の再建に努力しております。この際、このとき、この喜びをともにわかつことができず、戦争犯罪者として、あるいは内地に、あるいは外地に、プリズンに、また拘置所に、希望なく日を送つておりますることは、ひとり国民感情において忍び得ざるのみならず、またさらに国際友好上きわめて遺憾に存ずるところであります。(拍手)……一般国民は、戦争の犠牲を戦犯者と称せらるる人々のみに負わすべきでなく、一般国民もともにその責めに任ずべきものであるとなし、戦犯者の助命、帰還、釈放の嘆願署名運動を街頭に展開いたしましたことは、これ国民感情の現われと見るべきものでございます。
およそ戦争犯罪の処罰につきましては、極東国際軍事裁判所インド代表パール判事によりまして有力な反対がなされ、また東京裁判の弁護人全員の名におきましてマツカーサー元帥に対し提出いたしました覚書を見ますれば、裁判は不公正である、その裁判は証拠に基かない、有罪は容疑の余地があるという以上には立証されなかつたとあります。……また外地における裁判について申し上げましても、裁判手続において十分な弁護権を行使し得なかつた関係もあり、また戦争当初と事件審判との間には幾多の時を費しまして、あるいは人違い、あるいは本人の全然関知しなかつた事件もあると聞いておるのであります。
英国のハンキー卿は、その著書において、この釈放につき一言触れておりますが、その中に、英米両国は大赦の日を協定し、一切の戦争犯罪者を赦免すべきである、かくして戦争裁判の失敗は永久にぬぐい去られるとき、ここに初めて平和に向つての決定的な一歩となるであろうと申しておるのであります。かかる意見は、今日における世界の良識であると申しても過言ではないと存じます。(拍手)
かくして、戦争犯罪者の釈放は、ひとり全国民大多数の要望であるばかりでなく、世界の良識の命ずるところであると存じます。もしそれ事態がいたずらに現状のままに推移いたしましたならば、処罰の実質に戦勝者の戦敗者に対する憎悪と復讐の念を満足する以外の何ものでもないとの非難を免のがれがたいのではないかと深く憂うるものであります。(拍手)》(「官報号外」昭和27年12月9日)
発言中に引用されたハンキー卿の著『戦犯裁判の錯誤』は長谷川才次訳、時事通信社刊として独立直後の昭和27年(1952年)10月に日本語訳が出版され、大きな反響を呼んでいた。
占領中は、GHQの検閲によって東京裁判批判は一切禁じられ、東京裁判を肯定する趣旨の本しか出版されていなかった。しかし、講和独立後、言論の自由を回復するや、東京裁判を日本人の立場から批判する書籍が相次いで出された。昭和27年(1952年)には、日本無罪を主張したパール判事の「判決書」に関する田中正明著『日本無罪論―真理の裁き』(太平洋出版)、同著『全訳 日本無罪論』(日本書房)、弁護人だった瀧川政次郎著『東京裁判を裁く 上下』(東和社)などが出版された。更に、B・C級戦犯として無実の罪に問われた遺書・手記が、『あすの朝の“九時”―大東亜戦争で戦争犯罪者として処刑された人々の遺書』(日本週報社編)、『祖国への遺書―戦犯死刑囚の手記』(塩尻公明編 毎日新聞社)、『死して祖国に生きん―四戦犯死刑囚の遺書』(杉松富士雄編 蒼樹社)、『モンテンルパ―比島幽囚の記録』(辻豊編著 朝日新聞社)として出版された。これらの著編書を通じて、GHQによって隠蔽されていた戦犯裁判の実像が世に知られるようになっていたのである。
こうした情況を踏まえ、改進党の山下春江議員も国会決議の趣旨説明のなかで、
《…… 占領中、戦犯裁判の実相は、ことさらに隠蔽されまして、その真相を報道したり、あるいはこれを批判することは、かたく禁ぜられて参りました。当時報道されましたものは、裁判がいかに公平に行われ、戦争犯罪者はいかに正義人道に反した不逞残虐の徒であり、正義人道の敵として憎むべきものであるかという、一方的の宣伝のみでございました。また外地におきまする戦犯裁判の模様などは、ほとんど内地には伝えられておりませんでした。国民の敗戦による虚脱状態に乗じまして、その宣伝は巧妙をきわめたものでありまして、今でも一部国民の中には、その宣伝から抜け切れないで、何だか戦犯者に対して割切れない気持を抱いている者が決して少くないのであります。
戦犯裁判は、正義と人道の名において、今回初めて行われたものであります。しかもそれは、勝つた者が負けた者をさばくという一方的な裁判として行われたのであります。(拍手)戦犯裁判の従来の国際法の諸原則に反して、しかもフランス革命以来人権保障の根本的要件であり、現在文明諸国の基本的刑法原理である罪刑法定主義を無視いたしまして、犯罪を事後において規定し、その上、勝者が敗者に対して一方的にこれを裁判したということは、たといそれが公正なる裁判であつたといたしましても、それは文明の逆転であり、法律の権威を失墜せしめた、ぬぐうべからざる文明の汚辱であると申さなければならないのであります。(拍手)……》(「官報号外」昭和27年12月9日)
と、東京裁判を「文明の汚辱」とまで非難しているのである。
晴れて独立を達成した以上、戦勝国から勝手に押し付けられた「勝者の裁き」を受け入れる必要はないではないか。何故いつまでも無法の裁判による判決に従って同胞が刑に服さなければならないのか―という、勝者の無法に対する憤りとともに、歴史の自己解釈権を取り戻そうとする独立国家としての一種の高揚感がこれらの発言からは伝わってくる。
占領軍が約7年間にわたって日本国民に贖罪意識を持たせるべく日本軍の残虐さを宣伝し、あたかも国際法に基づいているがごとく東京裁判やB・C級裁判を強行したが、それにもかかわらず、それらの敵国の宣伝を鵜呑みにせずに、当時の日本の政治家の多くは自国の正義を信じ続けるだけの見識を持ち合わせていたのである。
■社会党議員による「東京裁判」批判
東京裁判を批判したのは何も保守政治家だけに限らなかった。決議採択に際して日本社会党の田万廣文議員は、
《私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されておりまする決議案に対して賛意を表明するものであります。……
私どもは、正義を愛し、平和を愛します。その意味から申しましても、この決議案に盛られた趣旨は正しいと考える。B級、C級の戦犯者こそは、すみやかに釈放せられるべき運命の星にあると私は考えるのであります。……》(「官報号外」昭和27年12月9日)
と訴えた。同じく日本社会党の古屋貞雄議員も、
《…… 戦争が残虐であるということを前提として考えますときに、はたして敗戦国の人々に対してのみ戦争の犯罪責任を追究するということ―言いかえまするならば、戦勝国におきましても戦争に対する犯罪責任があるはずであります。しかるに、敗戦国にのみ戦争犯罪の責任を追及するということは、正義の立場から考えましても、基本人権尊重の立場から考えましても、公平な観点から考えましても、私は断じて承服できないところであります。(拍手)……世界の残虐な歴史の中に、最も忘れることのできない歴史の一ページを創造いたしましたものは、すなわち広島における、あるいは長崎における、あの残虐な行為であつて、われわれはこれを忘れることはできません。(拍手)この世界人類の中で最も残虐であつた広島、長崎の残虐行為をよそにして、これに比較するならば問題にならぬような理由をもつて戦犯を処分することは、断じてわが日本国民の承服しないところであります。(拍手)
ことに、私ども、現に拘禁中のこれらの戦犯者の実情を調査いたしまするならば、これらの人々に対して与えられた弁明並びに権利の主張をないがしろにして下された判定でありますることは、ここに多言を要しないのでございます。しかも、これら戦犯者が長い間拘禁せられまして、そのために家族の人々が生活に困つておることはもちろんでありまするけれども、いつ釈放せられるかわからぬ現在のような状況に置かれますることは、われわれ同胞といたしましては、これら戦犯者に対する同情禁ずることあたわざるものがあるのであります。われわれ全国民は、これらの人々の即時釈放を要求してやまないのでございます。……》(「官報号外」昭和27年12月9日)
と切々と訴えた。
「敗戦国にのみ戦争犯罪の責任を追及するということは、正義の立場から考えましても、基本人権尊重の立場から考えましても、公平な観点から考えましても、私は断じて承服できない」―この正論は広く国民に受け入れられるものであった。革新を標榜していたとは言え、社会党代議士もまた、原爆投下という非人道的行為を敢えて犯しながら「文明」の名のもとに敗戦国を一方的に裁いた戦勝国の「正義」を唯々諾々と受け入れるほど、「卑屈」ではなかったのである。
この「戦犯釈放決議」は12月12日に今度は参議院でも可決された。
しかし連合国側が戦犯釈放になかなか同意せず、釈放の見通しも立たないまま1953年(昭和28年)に入り、緊喫の課題として、一家の主を失って困窮を極めている戦犯の遺族たちへの援助問題が浮上してきた。戦犯の遺族たちにも他の戦没者遺族と同じく弔慰金などの援助をするべきではないか、そのためには、戦争受刑者を犯罪者と見なすのではなく、公務で亡くなられた「公務死」と認定するべきではないかという議論が起こったのである。
7月21日、衆議院厚生委員会で、改進党の山下春江議員は、
《戦犯で処刑されました方々を公務死にいたしたいというのは、大体国会における全部の意見のように考えるのでありますが、政府はそれを公務死に扱うことは、いろいろ国際関係その他の情勢を勘案して、ただちに行うことはどうかというような答弁をかつてなさつたのでありますが、外務省はどういうお考えをお持ちになりますか。……国民としては、当然すでになくなられた方には上も下もなく同一に国家のために公務で死歿されたものと扱いたいのでありますが、そういうことに対する政府の見解をただしたいのであります。……》(第16回国会衆議院厚生委員会議事録第22号)
と質問した。これに対し翌22日、広瀬節男外務省参事官(大臣官房審議室付)が、
《[戦犯の刑死は公務死との考えに基づき]被処刑者の遺族の援護は、社会保障的見地から見ましてももつともなことだと思いますし、国際関係上から見ましても支障ないものと認めまして、外務省としては何らこれに異議はございません。こういうことを省議決定いたしましたことを御報告申し上げます。》(第16回国会衆議院厚生委員会議事録第23号)
と答弁している。現在の風潮から考えれば、政府・外務省が、連合国の軍事裁判において「侵攻戦争を行なった戦争犯罪人」と断罪された人々を犯罪者ではなく、公務で亡くなった人と認定しても「国際関係上から見ても支障ないと認める」と“省議決定” の上で断言したことはまさに驚くべきことだ。「東京裁判による刑死は実質的“戦死”である」という立場に、当時は政府も国民も立っていたのである。
遺族援護法改正に社会党は賛成した上にまた、熱心にこれを支持した。堤ツルヨ衆議院議員(右派社会党)は衆議院厚生委員会で、
《処刑されないで判決を受けて服役中の留守家族は、留守家族の対象になって保護されておるのに(注 既に成立している未帰還者留守家族援護法の適用を受けるの意)、早く殺されたがために、国家の補償を留守家族が受けられない。しかもその英霊は靖国神社の中にさえも入れてもらえないというようなことを今日の遺族は非常に嘆いておられます。……遺族援護法の改正された中に、当然戦犯処刑、獄死された方々の遺族が扱われるのが当然であると思います》(『靖国論集』p.114.)
と述べているが、「戦犯であっても靖国神社には戦没者としてお祀りするべきだ」というこの意見の前提に、「東京裁判は間違った裁判だった」という認識があることは言うまでもない。
保守・革新を問わず、国際社会に復帰した日本がまず行なったことが、戦犯釈放要求・戦犯遺族への年金受給という形での戦争裁判への異議申し立てであったことは、戦後日本の政治を考える上で忘れてはならないことではないだろうか。
■可決された「戦争犯罪」否定の国会決議
かくして1953年(昭和28年)8月、自由党、改進党、右派・左派社会党による全会一致で、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部が改正され、困窮を極めている戦犯遺族に対しても遺族年金および弔慰金が支給されることになった。一方、日本政府の熱心な働きかけによって、戦争受刑者の釈放も徐々に進んでいた。かくなる上は1日も早く残りの戦争受刑者も釈放しようと、当時の国会議員たちは1953年(昭和28年)8月3日、昨年に引き続いて再び衆議院本会議で、次のような「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」を可決した。
《8月15日九度目の終戦記念日を迎えんとする今日、しかも独立後すでに15箇月を経過したが、国民の悲願である戦争犯罪による受刑者の全面赦免を見るに至らないことは、もはや国民の感情に堪えがたいものがあり、国際友好の上より誠に遺憾とするところである。しかしながら、講和条約発効以来戦犯処理の推移を顧みるに、中国は昨年8月日華条約発効と同時に全員赦免を断行し、フランスは本年6月初め大減刑を実行してほとんど全員を釈放し、次いで今回フイリピン共和国はキリノ大統領の英断によつて、去る 22日朝横浜ふ頭に全員を迎え得たことは、同慶の至りである。且又、来る8月8日には濠州マヌス島より165名全部を迎えることは衷心欣快に堪えないと同時に、濠州政府に対して深甚の謝意を表するものである。
かくて戦犯問題解決の途上に横たわつていた最大の障害が完全に取り除かれ、事態は、最終段階に突入したものと認められる秋に際会したので、この機を逸することなく、この際有効適切な処置が講じられなければ、受刑者の心境は憂慮すべき事態に立ち至るやも計りがたきを憂えるものである。われわれは、この際関係各国に対して、わが国の完全独立のためにも、将又世界平和、国家親交のためにも、すみやかに問題の全面的解決を計るべきことを喫緊の要事と確信するものである。
よつて政府は、全面赦免の実施を促進するため、強力にして適切且つ急速な措置を要望する。
右決議する。》(「官報号外」昭和28年8月3日)
遠慮がちであった前年の国会決議に比して、この決議は独立国家としての自負心に溢れた、格段に力強いものになっている。提案趣旨説明に立った山下春江議員(改進党)は、
《…… 結局、戦犯裁判というものが常に降伏した者の上に加えられる災厄であるとするならば、連合国は法を引用したのでもなければ適用したのでもない、単にその権力を誇示したにすぎない、と喝破したパール博士の言はそのまま真理であり、今日巣鴨における拘禁継続の基礎はすでに崩壊していると考えざるを得ないのであります。(拍手)……「獄にしてわれ死ぬべしやみちのくに母はいますにわれ死ぬべしや」、このような悲痛な気持を抱いて、千名に近い人々が巣鴨に暮しているということを、何とて独立国家の面目にかけて放置しておくことができましよう。(拍手)機運はまさに熟しているのであります。》(「官報号外」昭和28年8月3日)
と切々と訴えた。「何とて独立国家の面目にかけて放置しておくことができましよう」の一節に、当時の日本人の思いが集約されているのではないだろうか。
平成5年(1993年)、細川護煕首相は「東京裁判の判決を受け入れることで日本は国際社会に復帰した」と述べたが、事実は全く違っていた。戦前・戦後の歴史を検証することなく行われた細川首相の答弁は、総理大臣としては恐ろしく無知にして無見識なものであった。
ともあれ、講和独立後の日本の政治家たちは、「勝者の裁き」を敢然と拒否することこそが「わが国の完全独立」と「世界平和」につながると信じた。勝者の裁きを否定して、連合国によって奪われた「歴史解釈権」を晴れて取り戻した「完全な独立国家」として国際親交に努めたい―これが紛れもなく戦後の日本政治の原点であったと言えよう。
なお、A級戦犯は昭和31年(1956年)3月31日までに関係各国の同意を得て全員出所したが、B・C級の最後の18名の仮出所が許され全員出所したのは昭和33年(1958年)5月30日のことであった。
■日本は「東京裁判」により法的に拘束されない
最後のB・C級戦犯が釈放された頃から、60年安保騒動に始まる反米親ソの革新勢力が台頭し、世の中は「革命前夜」の様相を呈してゆく。
このため、東京裁判否定の熱意を受け継ぐべき保守政治家たちは、米国との協調・友好を重視するあまり、米国の戦争責任追及=反米につながりかねない東京裁判否定論をトーンダウンさせた。一方、革新勢力は、ソ連・中国の歴史観に強い影響を受けながらマスコミや日教組と手を組み、“東京裁判史観”の普及に、これ努めることになったのである。
かくしてマスコミや革新勢力の支援の中で、GHQの協力を得て結成した日本教職員組合(日教組)が、GHQの「戦争犯罪周知宣伝計画」に基づいて作成された「歴史教科書」を使って行なう歴史授業によって、アメリカの「審判と慈悲に絶対的に従う」従属政権を樹立しようとするGHQの意図は、じわじわと日本の若い世代に浸透していくこととなった。
昭和57年(1982年)、歴史教科書の記述を文部省が検定で「侵略」から「進出」に書き換えさせたとして(これは後に誤報であることが判明した)、中・韓両国から大きな反発を招いた、いわゆる「教科書事件」が起こった。この時、近隣諸国から激しく批判された政府首脳、なかでも時の宮澤喜一官房長官(自民党)は、事実関係をろくに調べないまま、批判を全面的に受け入れた上、「わが国としては、アジアの近隣諸国との友好、親善を進める上でこれらの批判(韓国、中国からの批判)に十分に耳を傾け、政府の責任において是正する」という談話を発表するに至った。近隣諸国との友好のためには、東京裁判の判決に示された歴史観を受け入れるという、独立後の国会決議とまるで正反対の趣旨の談話が表明されたことになる。
以後今日に至るまで、残念ながらこの談話が追認される方向で進んでいるのである。
敵国によって“A級戦犯”とされた人々を靖國神社に合祀したことをめぐって再び近隣諸国を巻き込んだ形での問題が起こり、そのさなかの1985年(昭和 60年)11月8日 衆議院外務委員会で土井たか子議員(社会党)は「戦犯は日本も受けいれた東京裁判によって“平和に対する罪”で処刑されたのであり、戦没者とは違う。どうして戦犯を祀っている靖國に参拝するのか」と質問した。同じ社会党の先輩女性議員が、戦犯とされた人々が靖國神社にお祀りされていないことを嘆く遺族の人々の心情を代弁して、戦犯釈放運動を熱心に推進していたことなど、全く知りもしないのであろう。
この土井発言を補足するように、昭和61年(1986年)8月19日、衆議院内閣委員会で後藤田正晴官房長官(自民党)が、東京裁判について「サンフランシスコ対日平和条約第11条で国と国との関係において裁判を受諾している事実がある」と述べ、東京裁判の正当性を認めることが政府の統一見解であるとの考えを表明した。
この時期、サンフランシスコ講和会議でも問題とされた講和条約第11条に「裁判を受諾し」との一節があることから、日本政府は第11条のゆえに講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示された、いわゆる「東京裁判史観」の正当性を認め続けるべき義務があると、一部学者たちが強硬に主張していた。その主張に、土井氏や後藤田官房長官は安易に飛びついたものと思われる。
日本はサンフランシスコ講和条約によって「東京裁判史観」を受け入れたのかどうか。国際法の専門家である佐藤和男教授は国際法学会でのやり取りも踏まえ、次のように指摘する。
《第 11条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかった。日本政府は第11条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がない。
筆者は昭和61年8月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席した際に、各国のすぐれた国際法学者たちとあらためて第11条の解釈について話し合ったが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも上記のような筆者の第11条解釈に賛意を表明された。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはあり得ない」と語った。これが、世界の国際法学界の常識である。……
対日平和条約の発効により国際法上の戦争状態を終結させて独立を回復した日本の政府は、東京裁判の判決理由中に示された歴史観ないし歴史的事実認定―歴史の偽造(東京裁判のインド代表判事であったパール博士の言葉)として悪名が高い―を盲目的に受けいれる義務を負わず、いかなる批判や再評価をもその裁判や判決理由に下すことが自由であり、この自由こそが、講和を通じ代償を払って獲得した国家の「独立」の実質的意味なのである。》(『各法領域における戦後改革』p.100~101.)
講和独立後の日本の政治家たちは、「勝者の裁き」を敢然と拒否することこそが「わが国の完全独立」と「国際親交」につながると信じたが、それは「自己解釈権」を取り戻した独立国家として、極めて正当な行動であった。
こうした戦後政治の原点を踏まえ、私たちは、国際法上、敵国の軍事行動の一環であった「東京裁判」の判決に囚とらわれることなく、歴史の再検証と東京裁判の克服を堂々と世界に訴えていくべきなのである。そうすれば、いわゆる東京裁判史観を日本に強要したいと考えている中・韓両国などは猛然と反発するだろうが、その一方で本書で紹介したように世界の国際法学者や識者たちが、あるいは反東京裁判史観を奉じるインドを始めとするアジアの識者たちが、必ずや私たちの主張を断固支持・支援してくれるに違いない。
※終戦50周年国民委員会編、佐藤和男・青山学院大学名誉教授監修『世界がさばく東京裁判』「第6章」より転載。
なお、『世界がさばく東京裁判――85人の外国人識者が語る連合国批判』(定価1,600円+税、送料実費)は、日本会議でも取り扱っています。
[お問合せ先]
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-10-1-601
日本会議事業センター まで
メール= jc@nipponkaigi.org
FAX 03-5428-3724 TEL 03-5428-3723
![戦後政治の原点としての[東京裁判]批判](/images/main/opinion.jpg)
![戦後政治の原点としての[東京裁判]批判](/images/hx/h1-opinion.gif)