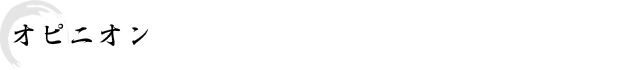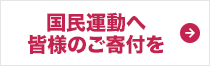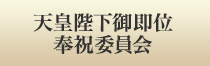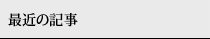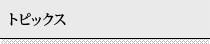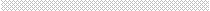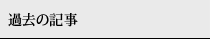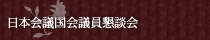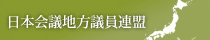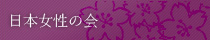皇室制度の抜本的見直しを目指して
大原康男 國學院大学教授
(※『日本の息吹』19年2月号より)
秋篠宮悠仁親王のご誕生によって、小泉純一郎前首相の下で性急に進められようとしていた皇室典範の改定はひとまず白紙撤回となったことは歓迎すべきであるが、だからといって、しばらくは皇室典範に関する議論を凍結してはどうかという声には賛成できるものではない。いや、今回の論議を契機として一般国民の間に俄[にわ]かに高まってきた皇室典範への関心が薄れないうちに、単に皇位継承問題だけでなく、戦後六十年の長きにわたって放置されてきた皇室制度の諸問題を抜本的に見直す機会となってほしい。
昨年三月七日、拙速な典範改定に反対するために日本武道館で開催された「皇室の伝統を守る一万人大会」での決議に応じて、十月十七日に発足した超党派の「皇室の伝統を守る国会議員の会」(島村宜伸会長)がその先駆的役割を果たすものと期待されている。現憲法・典範下の皇室制度全般について政治が本格的に目を向けるようになったのは画期的なことである。これまで繰り返し述べてきたことだが、そこで検討されるべき主要な事項についてあらためて拾い上げておくことにしたい。
●GHQは皇室制度をいから改変したか
戦後六十年も放置されてきたと先に述べたが、いうまでもなく、戦後の皇室制度は米国を中心とした連合軍総司令部(GHQ)の手によって周到に構築された。これから取り組むべき制度見直しのためには、その概要を瞥見しておく必要があるだろう。それは大きく分けて以下の三つの側面から成っている。
(1)法的・政治的側面
天皇の政治的・軍事的権能を剥奪し、天皇の地位を「統治権の総覧者」から「国政に関する権能を有しない象徴」に変更するとともに、それに見合った皇室制度を樹立すること。これは最終的には日本国憲法ならびに新しい皇室典範を制定することによって完結した。
(2)経済的側面
皇室を財閥の一種と見做[みな]して皇室財産のほとんどを国有財産に編入するとともに、皇室経費のすべてを国会のコントロール下に置いて、皇室の経済的自立の基盤を喪失させること。これは皇室財産の凍結、多額の財産税の賦課、皇族の経済的特権の剥奪等の措置を経て、憲法および皇室経済法によって法的に確立した。
(3)精神的側面
あらゆる手段を駆使して国民の天皇崇拝意識を除去すること。これは神道指令の発出、修身・地理・国史教育の停止、いわゆる〝人間宣言〟詔書の発布、御真影の回収と奉安殿の撤去、宮城遥拝や聖壽万歳の禁止、教育勅語の排除、祝祭日の改変等々の措置によって執拗に実施された。
本稿で扱う課題は主として(1)と(2)の領域に限定し、(3)については別の機会に譲るが、まず、何よりも指摘しておかねばならないのは、その中心をなす現憲法と現典範の法的な性格である。現憲法は、旧憲法七十三条に定める改正規定、すなわち勅命による議案の議会への付託、両議員の総数の三分の二以上の出席と三分の二以上の議決。さらに天皇の最高諮問機関たる枢密顧問の諮詢という六十五条の手続きを経て成立している。これは現憲法と旧憲法との間に法的連続性が明確に存在していることを意味する。
これに対して、現典範は、皇族会議および枢密顧問の諮詢を経て天皇が勅定するという旧典範六十二条の改正手続きをとらず、旧典範がなお効力を有していた時期に議会によって別途に一個の新法律として制定され、昭和二十二年一月十六日に公布された。ために、その手続きが一時問題にされたことがあるものの、結局、旧典範は、それに基いて制定された皇室令などとともに新典範が施行される前日の同年五月二日に廃止されている。この経緯で明らかなように、現典範は旧典範を改正したものではなく、両者の間には法的連続性はない。これが憲法との大きな違いである。
この違いは双方の法体系の違いから来ている。旧典範は、憲法を頂点とし法律・勅令などから構成される「国務法」と皇室典範を頂点とし皇室令・宮内省令などから構成される「宮務法」という「二元的法体系」の下で、憲法と対等の位置にあったのに対し、現典範は、戦後日本の法制が憲法を頂点とする「一元的法体系」に変わったことによって、同じ「皇室典範」の名でありながら、憲法の下の一法律として位置づけられているからである。
同じ大臣でありながら宮内大臣は内閣の構成員ではなく、皇室の官吏と政府の官吏はそれぞれ別系統であり、皇室の事務は政府の事務から一線を画すという「宮中と府中の区別」の考えが貫かれていた、これを宮中の側からみれば、「皇室の自立性」が確保されていたことになる。
このような認識を前提としつつ、具体的なことがらに入ってみよう。
●憲法上の不備~元首、国事行為、祭祀、財産
いうまでもなく、第一は憲法である。外国軍の占領という未曾有の異常事態の下で外国人によって草案が作られたという特異な出自のゆえに、わが国の歴史・伝統にそぐわないものであることはいまさら多言を弄するまでもないが、第一に取り上げねばならないのは、天皇が「元首」であることを明記する規定が不備であることだ。
これまでの政府見解では対外的には「元首」であることを認めているが、国内的には今もなお曖昧な態度に終始しているため、たとえば、外国の元首が来日し、自衛隊の儀仗を受ける際に同行されないといった非礼なことが依然として行なわれているし、国会開会式に天皇が出席なされることを拒否し続ける共産党の主たる〝論拠〟ともされている。来たるべき憲法改正での重要な課題の一つであろう。
次に、憲法六条・七条に列挙されている「国事行為」が取り上げられねばなるまい。たとえば、自国の大使・公使に対して信任状を発するのは内閣であって、天皇は単にこれを「認証する」にとどまるが、外国の大使・公使を「接受」して信任状を受理されるのは天皇であり、守備一貫性を欠いた構成であることは歴然としている。
また、「国事行為」がすべて「制限的列挙」とされているために、これに類する別の事象が生じたとしてもその対象とはならず、やむを得ず「象徴としての公的行為」という新たなカテゴリーを創案してことを処理する解釈・運用がなされてきた。たとえば、「新年祝賀の儀」は「国事行為」に該当する「儀式を行なうこと」であるが、「全国戦没者追悼式」や「全国植樹祭」などへのご臨席は「象徴としての公的行為」として行なわれる。
奇妙なことに、右に述べた外国の大使・公使の「接受」が前者であるのに対し、その任命権者である外国元首をお迎えするのは明文の規定が存在しないために、後者という一ランク低い行為として扱われるという矛盾が生じている。このような整合性の無さを解消し、「国事行為」全般を整理し直すことに着目すべきではないか。
いまさら口幅[くちはば]ったく申すまでもなく、「皇室祭祀」は悠久の昔から歴代の天皇が国の祭り主として天神地祇を祀り、「国安かれ、民安かれ」と国家・国民の安寧慶福を祈ってこられた国家第一の公事であった。国の祭り主の地位こそが天皇を天皇たらしめる源泉であると言って過言ではない。
ところが、敗戦とGHQの占領政策によって、それは単なる皇室の「私事」として取り扱われるようになった。「皇室祭祀」を「公事」として扱うことは憲法二十条・八十九条に定める政教分離原則に違反するとの憲法解釈によるが、それも昭和五十二年に言い渡された「津地鎮祭訴訟」最高裁判決が提示する柔軟な限定的分離主義に基いた「目的効果基準」の法理を忠実に適用すれば、十分に乗り越えられよう。
いや、かつて大金益次郎元侍従長が「皇室祭祀」のことを「象徴たる天皇の行事であると私は思っております。またかくのごとき行事があればこそ、天皇が象徴であるということのほんとうの意義が生れて来るのではなかろうかと私は思うのであります」と述べたように、むしろ象徴天皇制を支える基盤であると積極的に考えるべきではなかろうか。
一方、既述したように、GHQは皇室の「経済的自立性」を削ぐために意を注いだが、それは単に過去に蓄積された皇室財産を解体するにとどまらず、将来にわたって再び皇室財産が形成されることを防ぐために設けられたのが憲法第八条の次のような規定である。
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
すなわち、国民が財産を「譲り渡し」、皇室が「譲り受け」るということの累積によって皇室がその経済的基盤を確かなものにすること、ならびに、皇室からの財産の「賜与」が政治的・社会的に大きな影響を与えることを防ぐために、これらを国会の全面的な統制下に置こうとしたのである。
しかしながら、世界中のどの君主国を眺めてみても、王室の財産権に関して、あたかも「成人被後見人(かつての禁治産者)」に対するような制限を加える規定を設けているような憲法はない。占領下はやむを得なかったとしても、本来は占領終結と同時に撤廃されるべき時限的立法として扱うべきであろう。
その一方で、皇室にはさまざまな税が課せられているのである。とりわけ、記憶に残っているのは昭和天皇の遺産に対する相続税の課税である。当時、宮内庁は、課税対象額は約十八億五千万円、配偶者控除を受けられた皇太后陛下(香淳皇后)の納税はなかったが、天皇陛下は株式などを売却して納税されたと発表した(金額は公表されていないが、約四億二千八百万円といわれている)。この課税の背景には、これまでずっと皇室が住民税(都民税・区民税)などを収めて来られた実績を念頭に置いているようである。
だが、考えてもみよ、一般国民は法に触れなければ財産の取得も処分も全く自由に行なうことができるが、皇室には先記した憲法八条の厳しい制限が存在するにもかかわらず、納税の義務は国民と同様に負担されるというのでは、極めて不公平だと言わざるを得ない。憲法八条をただちに廃止することができないならば、せめて税制上の是正措置だけは早急に行なうべきではなかろうか。
●皇室典範及び法令上の不備
皇室典範の方に話を転じよう。今、最も関心を持たれている皇位継承問題は、小泉内閣時代に設けられた「皇室典範に関する有識者会議」がまとめた女系皇族にも皇位継承権を認めるとの報告書を安倍晋三首相が白紙に戻す方針を正式に決定したことによって、ひとまず落ち着くものと思われる(「産経新聞」平一九・一・三)。しかし、皇位継承の安定的確保の課題は依然として残っており、報告書の結論とは根本的に違った男系主義による皇統維持について検討することが早急に求められよう。
その現実的な方策は、私を含めて少なからぬ人々が提唱していることだが、先に述べたGHQの経済的な圧力によって、昭和二十二年十月十四日に皇族たるの身分を離脱することを余儀なくされた元皇族の男系のご子孫のうち、年齢や経歴などから見て適切な方に皇族の身分を取得して頂き、傍系から皇位継承を支えてきた宮家の拡充を図ることである。現典範十五条は「皇族でない者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」と定めるが、典範は改正することなく、皇籍取得・新宮家創設を特例として認める臨時立法を行なえばことの決着は可能である。
皇位継承に関して付け加えておくと、現典範は旧典範には明記されていた皇位継承に関わる重儀である神器の継承や大嘗祭に関する規定を欠いている。そのために、昭和から平成への御代替わりにおいては国会の内外で激しい論議の標的となったり、大嘗祭については数件もの訴訟が起こされたりもした。これらの訴訟はすべて最高裁で棄却されているので、そうした実績をも踏まえて法の不備を早急に補わねばなるまい。
法の不備といえば、これだけではない。旧典範の下では皇室令以下の附属法令が体系的に制定されていた。このうち主要な皇室令を列挙すると――皇籍(皇統譜令)、皇位継承(登極令)、摂政設置(摂政令)、立太子(皇儲令)、成年(皇室成年式令)から、親族関係(皇室親族令)、皇族一般(皇族身位令・皇族会議令・皇族就学令など)、宮中の祭祀・儀礼・服制(皇室祭祀令・皇室儀制令・天皇ノ御服ニ関スル件など)、葬制・墓制(皇室喪儀令・皇室陵墓令・皇室服喪令など)、経済(皇室財産令・皇室会計令など)、そして宮中の諸官制(宮内省官制・御歌所官制など)、宮内官の任用・待遇(宮内官任用令・宮内官懲戒令など)に至るまで、ほぼ完璧に整備されていたことが分かる。
これに対して、現典範と相前後して施行された皇室関係法令は、(新)皇統譜令、皇室経済法、皇室経済法の施行に関する法律(皇室経済法施行法の前身)、宮内府法(宮内庁法の前身)などごく限られている。占領が集結した後に新たに制定されたのは、国事行為の臨時代行に関する法律と元号法ぐらいである。この惨状はまさに国会ならびに政府の立法懈怠によるものである。
ただ、当時の宮内府は応急措置として新典範が発効した五月三日に文書課長名で「皇室令及び附属法令廃止に伴い事務取扱に関する通牒」を発している。この通牒は五項目から成っているが、その第三項には「従前の規定が廃止となり、新しい規定ができていないものは、従前の例に準じて、事務を処理すること」とあり、例として「皇室諸制典の附式、皇族の班位等」が掲記されている。これに基いて、たとえば、歌会始や講書始の儀、皇族の成年式やご結婚の儀、立太子礼、昭和天皇のご大喪、今上天皇のご大典などが旧皇室令に準拠して行なわれたのである。
法整備が全然進まない中で制度の欠陥を補うために、こうした行政実例が積み重ねられたのはまことに貴重な実績だと言えるが、やはり明文の規定が存在することが本来のあり方である。遅まきながらも、これらの実績を踏まえて早急に立法化を進めるべきであろう。
また、旧憲法の下では男子皇族は成年に達すれば貴族院議員に就任されるとともに(貴族院令)、枢密院会議に列席される一方、原則として陸海軍の武官に任じられることになっていた(皇族身位令)。そのために皇族に対する教育上格別の配慮がなされ、皇室就学令をはじめとする法令の制定や、皇子付き職員ないし東宮・皇子傅育官の設置、宮内大臣による学習院の管理など(学習院官制)、さまざまな制度が整えられていた。
しかるに、現憲法下では皇族の役割については法令に何の規定もない。それでも皇族方は「国民統合の象徴」である天皇をお扶[たす]けする準象徴として、これまで国際親善や慈善・福祉・学芸活動、あるいは多くの国家的行事へのご出席など、各方面で尽力されてきた。
同じように皇族に対するご教育についても何ら定めはなく、学習院も今日では一私立学校に過ぎない。周知のように、今般の典範改定論議では皇嗣に対する「帝王学」がしきりに強調された。そのことに異を唱えるつもりは毛頭ないが、何よりもまず戦後ほとんど顧慮されることのなかった皇族一般に対する特別のご教育の充実・整備が肝要であろう。「帝王学」はその基盤の上に加えられるべきものである。
最後に現行法の致命的な欠陥を挙げておこう。それは皇室にとって最も関心の深いことがらであるはずの皇室典範の改正に、皇室のご意向を反映させる法的な回路が全くないことである。旧典範の改正には皇族会議の議を経ることになっていたが、現典範は一法律に過ぎず、単なる国会の議決によってなされるからである。ご自身の地位や処遇の変更について何らの発言権もないというのは、このような文脈では使いたくはないが、これほど〝非民主的〟な制度はないと断言できる。
本来は単なる法律ではない、憲法に直属する特別法として位置づけ、皇室のご意向が反映できる規定を設けることが望ましいが、それが当面困難ならば、せめて現典範に「皇室典範の改正は皇室会議の議を経る」というような規定を置くべきである(皇室会議には議員として皇族の代表二名が参加されるから)。典範の具体的な改正論議はそれが実現してからのことではないか。