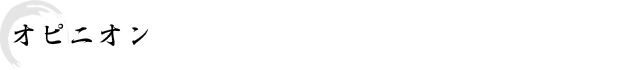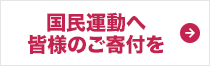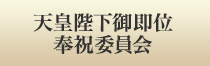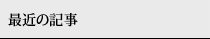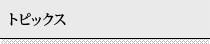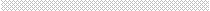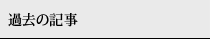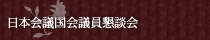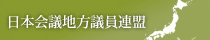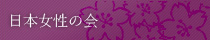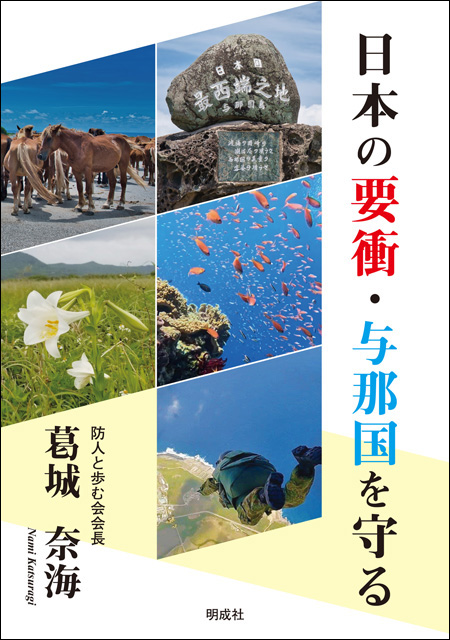世界からみた靖国神社
(平成9年8月)
「靖国神社が日本の戦歿者追悼の中心施設である」ことは世界の常識なのに、その事実を我が国の為政者及び一部マスコミはなぜ認めようとしないのか。
▼ 我が国の戦歿者追悼の中心施設はどこなのか
平成九年四月二日、「愛媛玉串料訴訟」上告審で、最高裁大法廷は「たとえ戦歿者遺族の慰藉が目的であっても県知事が靖国神社などに玉串料を公費から支出したことは憲法が禁止した宗教活動にあたり、違憲である」という判決を下した。この判決をめぐって、第一審から憲法学者として一貫して関わってこられた日本大学の百地章教授にインタビューした時のことである。
十五人の最高裁の判事のうち、実に十三人が違憲と判断したことについて、百地教授はこう述べている。
「靖国神社についても『戦前は確かに戦歿者慰霊の中心施設だったかも知れないが、戦後は単なる一神社、一宗教法人になったんだから、そんなの特別扱いする必要はない』という発想をもつ人たちが中心となって判決を書いてしまった――これが今回の判決の特徴ではないか」
実際、判決文は、「他の宗教団体でも戦歿者を祀っているところはあるではないか。なぜ靖国神社にこだわるのか」として、靖国神社だけを特別扱いすることに疑問を呈し、国家としては別の戦歿者追悼のあり方を模索すべきだと問題提起している。
この意見に対して、百地教授は「戦前・戦中はもちろん戦後も靖国神社が国家の戦歿者追悼の中心施設であり続けている現実を無視している」として、こう反論している。
①明治二年に、国事に斃れた戦歿者を祀るため靖国神社の前身である東京招魂社がつくられた。明治十二年に靖国神社と改称して、以後、現実に国家の慰霊施設として戦歿者が祀られてきた。
②戦後も、靖国神社に誰を祀るかということには厚生省がかかわってきた。また、地方自治体も遺族に対する慰藉を理由に、靖国神社参拝のための旅費を支援したり、護国神社への玉串料を公費から支出してきた。
③外国要人の参拝も明治二十年代から戦後の今日までずっと続けられている。外国の元首や軍人あるいは大使、公使が訪日したり着任したりする際には参拝しており、諸外国も靖国神社を公的な戦歿者慰霊の中心的施設として評価している。
つまり、たとえ宗教的性格を帯びていようとも、靖国神社は我が国における公の戦歿者追悼の施設として認められてきたのであって、その現実に即して国や地方自治体が相応の関与をすることは合憲だと、百地教授は訴えたのである。
この③の、外国の元首や政治家たちが参拝している事実があるということを聞いて、驚いた私は思わず聞き返した。「そうした記録はあるんですか」。
すると、百地教授はおもむろに一冊の資料集を取り出してきた。『靖国神社外国人参拝記録〔明治二十年~平成七年〕』という冊子で、明治二十年以降、正式参拝をした外国人の記録である。その一覧を見て、これほど多くの外国要人が靖国神社に参拝していたのかと驚いた。
この冊子は、外国から見ても靖国神社が戦歿者追悼の中心施設であることを傍証することを目的として靖国神社と神道政治連盟が協力して作成したもので、平成八年十二月、被告側の準備書面資料として最高裁大法廷に提出された。当然のことながら、一般の目には触れていない。このまま埋もれてしまうには余りにも惜しい。そこで、靖国神社と神道政治連盟の許可を得て、その一部をここに紹介したい。
▼ 外国要人第一号はタイの外務大臣
どこの国でも、祖国を守るために斃れた戦死者に敬意を表する場所がある。それはシュライン(=寺院〈宗教的施設〉、日本の靖国神社や中華民国台湾の忠烈祠、スペインのホーリー・クロス、イギリスのウェストミンスター寺院等)の形をとったり、メモリアル(=記念館、オーストラリアの首都キャンベラにある「戦争記念館」、アメリカ・真珠湾の「アリゾナ記念館」等)になったり、広大な国立墓地(アメリカのアーリントン墓地、韓国の国立墓地、インドネシアのカリバタ英雄墓地等)であったり、あるいは無名戦士の一遺体で全体を代表させたり(イギリス、フランス等)と、形は多様であるが、それらは、国民の魂のより所とも言うべき聖地になっている。(名越二荒之助著『新世紀の宝庫・日本』)
いかなる宗教を持とうとも、国のために亡くなった人々の魂を鎮める場所を求めるのは世界共通の心情なのであり、近代国家の成立とともに世界各国はそれぞれの伝統に基づいて戦歿者追悼の国家施設を生み出してきたのである。
そして、交通手段の発達とともに外交使節や政治家の往来が活発化し、相手国を訪れた際には戦歿者追悼施設に敬意を表することが外交儀礼のひとつとして重視されるようになった。我が国が靖国神社を建立した明治時代は、世界的にもまさにこうした時代であった。
靖国神社に初めて公式参拝した外国要人は、シャム(タイ)国王の弟で外務大臣のデヴァウォングセ閣下で、明治二十年九月二十二日のことである。そして我が国が国際政治の表舞台に登場することになった日露戦争以降、外国要人の参拝は本格化する。アメリカ・ハーバード大学名誉総長エリオット博士(明治四十五年七月十日)を筆頭に、イギリス軍司令官バーナジストン少将(大正三年十二月十四日)、フランス航空将校団(大正八年一月十九日)、ロシア将校チホプラゾフ中佐(八年七月三十一日)、第一次世界大戦時の連合国軍最高司令官でフランス人のジョッフル元帥(十一年一月二十二日)など、やはり軍人が多い。
また、王族も、ルーマニアのカロル皇太子殿下(大正九年七月七日)、イギリスのエドワード・アルバート皇太子殿下(後のエドワード八世、大正十一年四月十八日)、スウェーデンのグスターフ・アドルフ皇太子同妃両殿下(同十五年九月十二日)、イギリス国王ジョージ五世第三王子グロスター公ヘンリー殿下(昭和四年五月五日)、シャム皇弟アロングコット参謀総長(同四年十一月二十六日)、デンマーク皇太子クリスチャン同妃両殿下、皇弟ハラルド同妃両殿下(同五年三月十八日)、シャム皇弟ラマ六世同妃両殿下(同六年四月八日)、スウェーデン王子カール殿下(同八年六月二十二日)、タイ王族ワンワイ・タヤコーン・ワラワン殿下(同十六年四月二十八日)と次々に参拝に訪れている。
ほかにも昭和に入ると、毎年のようにフランス、イタリア、アメリカ、ドイツやペルー、アルゼンチンなどの軍人が参拝のため訪れている。欧米から来るのに船旅で一カ月以上かかったこの時代に、これだけの王族や軍人が来日し靖国神社に参拝していた事実は、我が国の国際的地位の向上を示すものであろう。なお、アジアの要人の参拝がないのは、シャム(タイ)を除くすべての民族が欧米の統治下にあり、独立国家でなかったためである。
▼ 何とリットン調査団も正式参拝
参拝名簿を眺めていると、王族・軍人以外にも、意外な人が参拝をしていることに驚かされる。
昭和六年八月二十七日、大西洋単独飛行で有名となったアメリカの飛行士リンドバーグ夫妻が参拝に訪れている。
昭和七年三月二日、イギリスのリットン卿一行が参拝しているのも興味深い。言うまでもなくリットン卿一行とは、国際連盟リットン調査団のことで、我が国の満洲政策を実地に調査し、批判的な調査報告書を提出したことでよく知られている。我が国の行動を非難したグループでも、靖国神社には正式に参拝している事実を知る時、戦争の評価とは無関係に、戦歿者に敬意を表することが国際儀礼であることを改めて実感させられるとともに、「靖国神社こそが軍国主義の淵源である」という後のGHQの考え方が、決して当時の国際社会の常識ではなかったこともわかる。
昭和十二年二月十八日には、国賓待遇で来日したローマ法王代表使節カーディナル・ドハティ師が参拝している。戦前は国家神道の時代と言われ、他の宗教を弾圧した暗い時代ということになっているが、こうしてキリスト教の代表者も堂々と参拝しているのである。「靖国神社を頂点とする国家神道が他の宗教を弾圧した」とする見方はやはり再検討されねばなるまい。
さて、昭和十六年十二月八日の大東亜戦争勃発とともに、参拝する外国要人の顔触れもがらりと変わっている。我が国の同盟国の要人と、大東亜戦争を契機に欧米宗主国の軛くびきから脱し、独立を獲得し始めたアジア諸民族の代表者たちが次々と参拝しているのである。
開戦四日後の十二日には、ドイツ大使とイタリア大使がそれぞれ参拝し、十九日にはルーマニア大使も参拝している。以後、ブルガリア公使、ビルマ行政府長官バー・モウ閣下、タイ外務大臣ウイチット・タワカーン閣下、フィリピン独立準備委員長ホセ・P・ラウエル閣下、自由インド仮政府首班チャンドラ・ボース閣下、ジャワ中央参議院議長スカルノ閣下等の名前が見える。
靖国神社外国要人参拝記録は、国際社会における我が国の立場をそのまま見事に反映していると言えよう。
▼ 靖国神社を救ったバチカン公使代理ビッター神父
未曾有の敗戦の中で、敵・連合国のGHQは我が国を占領し、「再びアメリカを始めとする連合国の脅威とならないようにする」ため、我が国の諸制度に根本的な改変を加えてきた。特にGHQの中には、軍国主義・超国家主義を廃絶するという観点から、靖国神社と護国神社の廃絶を主張する者もいた。
しかし、ポツダム宣言で保障した「信教の自由」という建前はもちろん、それ以上に靖国神社・護国神社の存続を願う一般国民の願いを無視することはできず、神社の廃絶まではいかなかった。
特に神道に対して敵意丸だしの神道指令を起草したGHQの民間情報教育局(CIE)の幹部は、当初、神社の祭典は軍国主義的な行事や扇動的な説教があると思い込んでいたようであるが、終戦直後の昭和二十一年二月、靖国神社の祭典を視察した際、軍国調とはおよそかけ離れた静かで簡素な、しかも清浄な感じのものであったため、予想に反した強い印象を受け、これがきっかけとなって、靖国神社のみならず神社神道に対するGHQの認識が大きく変わったようである。(大原康男著『神道指令の研究』)
また、終戦当時、駐日ローマ法王代表バチカン公使代理であったブルーノ・ビッター神父の存在も忘れることはできない(以下参考、木村正義「靖国神社とブルーノ・ビッター神父」、社報『靖国』昭和五十六年七月号所収)。
GHQは日本占領直後、当然のことながら靖国神社の処置問題を取り上げ、司令部内では「焼却すべし」という意見が大勢を占めた。そして、その最終的判断は、マッカーサー総司令官に任されることになった。マッカーサーは決断を下すにあたって、キリスト教会の意見を聞くこととし、ビッター神父に対し、靖国神社処分に対する使節団の統一見解を文書をもって回答されたい旨要望した。
第一次大戦の勇士で陸軍中尉、ドイツ敗戦後聖職者の道を選び、昭和九年から日本に滞在、上智学院の院長も務めた知日派のビッター神父は次のように答申した。
《自然の法に基づいて考えると、いかなる国家も、その国家のために死んだ人びとに対して、敬意をはらう権利と義務があるといえる。それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない。無名戦士の墓を想起すれば、以上のことは自然に理解出来るはずである。
もし靖国神社を焼き払ったとすれば、その行為は、米軍の歴史にとって不名誉きわまる汚点となって残ることであろう。歴史はそのような行為を理解しないに違いない。はっきりいって、靖国神社を焼却する事は、米軍の占領政策と相いれない犯罪行為である。》
マッカーサー司令官はこの答申を受けて、靖国神社の焼き払いを中止せしめたという。
かくしてGHQは、①敗戦後も、靖国神社が日本の戦歿者追悼の中心施設であることを日本の大多数の国民は認めており、②その祭典は決して軍国主義を賛美するものではなく、③バチカンの代表者も、たとえ宗教的色彩を帯びようとも靖国神社は戦歿者追悼の施設である以上、その存続を認めるべきだと考えている――ことを知り、その廃絶は断念したのである。
▼ 独立後、最初に正式参拝したのはアメリカ軍人
我が国を侵略国として非難するためにGHQが開催した政治ショウである極東国際軍事裁判(東京裁判)の効果もあって、国際社会において我が国は残虐な侵略国家との烙印を押されることとなった。当然のことながら、靖国神社に対しても圧倒的なマイナス・イメージを植え付けられてしまった。それでも、肉親を戦争で亡くした日本人の大多数は靖国神社に対する崇敬の思いを変えることなく、国家による靖国神社護持を強く政府に求めていく。
一方、GHQの政治宣伝に惑わされることなく、靖国神社を日本の公的な戦歿者追悼施設と見なす外国要人(在日米軍幹部を含む)も決して少なくはなかった。神道指令とその影響を受けた現行憲法の拘束があり、日本政府は表向き靖国神社にかかわることはできなくなり、訪日する外国要人に靖国神社参拝を勧めることは難しい事態となった。このため、戦後、靖国神社に参拝した外国要人たちのほとんどは自ら望んで参拝したのであり、その意味でその行動は外交的な儀礼にとどまらず、我が国の戦歿者に対する、特別な思いの現れとして受け止めることができよう。
我が国が講和独立を果たした後、正式に氏名を記帳の上参拝した外国人は、昭和二十九年三月三日のアメリカ軍陸軍大佐ウィリアム・フリベリック氏が初めてである。以後、国連軍首席参謀ジェームズ・ターレント陸軍大佐や世界戦争参加者同盟(WVF)の秘書長代理や事務局次長、オーストラリアの政治家などが次々と参拝している。
政府関係者の正式参拝は、昭和三十三年二月四日のパナマ共和国駐日大使リカルド・マルテネッツ閣下が初めてである。同年の九月十一日には駐日コロンビア代理大使ヒラルド・ロンドニヨ閣下も参拝している。アメリカの強権的なやり方をよく知る南米諸国はその反動からか、意外と親日的な傾向が強いようだ。
▼ 外国元首として初めて参拝したアルゼンチン大統領
戦後、外国元首としての公式参拝は、アルゼンチン共和国のフロンディシ大統領をもって嚆矢とする。
昭和三十六年十二月、国賓として来日した大統領夫妻は天皇陛下主催の宮中晩餐会に臨まれた翌十五日、まず明治神宮に参拝、その後、靖国神社を訪れた。大統領夫妻は随員三十七名と同国実業団約百名を従えて神門前に到着、参道両脇に参列する遺族ら約一千人が日の丸の旗を振って歓迎する中を静かに拝殿に進んだ。ご夫妻は花輪を神前に奉奠して参拝した。参拝が終わると、参道両側に並んでいる遺族らと握手を交わし、両国の万歳が三唱される中、拍手に送られてお帰りになった。
以後、昭和三十八年六月四日、国賓として来日したタイのプミポン国王夫妻が御内意をもって代理を参拝させたほか、昭和四十八年十一月八日にはトンガ王国国王タウファアハウ・ツポウ四世同妃両陛下が参拝されている。
また、昭和五十五年十一月一日、国家元首ではないが、チベット・ラマ教法王ダライ・ラマ十四世が特に望んで参拝されたほか、ソ連崩壊に伴い独立を回復したリトアニア共和国のアドルファス・スレジェベシス首相夫妻がやはり「日本の戦歿者に敬意を表したい」という本人の強い希望で平成五年九月二十一日に参拝している。
わが国に訪れる外国元首の数から考えれば、決して多いとは言えないが、これは、GHQの占領政策の影響を受けた政府外務省が「靖国神社は日本の公的な戦歿者慰霊施設ではない」という考えをもっているからである。実際にアメリカのアイゼンハワー大統領が参拝して日本の戦歿者に敬意を表したいと要望したのに対し、外務省が難色を示して潰れたことがある。いわゆるA級戦犯合祀問題で中国などから首相の公式参拝を批判された昭和五十四年以降は、参拝を公式日程に入れることを希望した元首級の要人に対して、外務省が婉曲的に反対。そのため元首クラスの参拝は、ほとんど実現を見ていないのである。
もっともいわゆるA級戦犯問題が外国要人の参拝の障害になっているのはその日程作成に外務省が関与する元首クラスの時だけで、日本の外務省と無関係に、自主的に参拝に訪れる要人も多い。
戦後から平成七年までに正式に記帳した上、参拝したケースは二百三十三件。そのうち首相・閣僚クラスの参拝は十三件(国別の内訳は、首相クラスが中華民国、ビルマ、トンガ王国。閣僚クラスがビルマ、トルコ、イタリア、チリ、ベトナム、インドネシア、パラオの七ヵ国)。外交官による参拝は十六ヵ国、十八件。武官による参拝は十カ国、二十六件。国会議員や知事クラスの参拝は十三件ある。また、大佐クラス以上の軍人による参拝は十六ヵ国、五十九件ある。
この数を多いと見るか少ないと見るかは見解の分かれるところだろうが、先に述べたように日本の外務省が消極的反対の立場に立っていることを考えるならば、参拝した要人たちはみな自主的に靖国神社を訪れたのであり、我が国の戦歿者に対する並々ならぬ敬意の現れとして積極的に受け止めたいと思うのである。
教科書問題が起こった昭和五十七年以降も、公的資格をもつ要人だけでも、エジプト国会議員で前世界イスラム審議会事務総長モハメッド・トゥフィク・オーエイダ博士、米国ハワイ州知事ジョージ・アリヨシ夫妻、ドイツ連邦共和国大使館国防武官、チリ国通産大臣ルネ・アベリウク閣下、フィンランド特命大使カリ・ベルホルム閣下、在日スリランカ大使C・マヘンドラン閣下等々が訪れている。
また、アメリカ空軍横田基地司令官などの在日米軍幹部もよく参拝に訪れており、アメリカはその数も十八件と最も多い。次いで軍人の参拝が多いのがドイツで、十三件にのぼる。同じ敗戦国としての親近感からなのか、ドイツ駐日大使館付武官は着任離日に際しては必ず参拝している。その伝統は今に受け継がれ、平成八年八月十三日、離任にあたってドイツ駐日武官のロベルト・ウェルナー陸軍大佐が、イラン一等書記官のM・シャケリ氏とともに正式参拝している。
▼ 外国の練習艦隊・士官候補生たちの正式参拝
世界各国の練習艦隊が遠洋訓練の途中、日本に立ち寄り、日本の戦歿者に敬意を表するべく靖国神社に正式参拝するケースも多い。
戦後初めて正式参拝に訪れた外国軍隊は、フランスの練習艦隊であった。昭和三十八年二月十一日午前九時、遠洋訓練の途中、日本に立ち寄った巡洋艦ジャンヌ・ダルク号、護衛艦ビクトール・シェルシエ号の士官候補生及び乗組員百六十名は分乗したバスから降りて、神門前に整列。軍楽隊を先頭に隊列を整えて発進した。真っ白な手袋にゲートル、礼装用の剣を携え、中庭に参進。横隊に整列し、修祓の後、ジャンヌ・ダルク号艦長ストレリー大佐が本殿木階下に花輪を奉奠、この時ストレリー大佐以下全隊員軍楽隊の奏楽とともに捧げ銃をし、一分間の黙祷を捧げた。
拝礼後、大佐以下全員が、靖国神社の案内で宝物遺品館(まだ遊就館は開館になっていない)を見学した。特に東郷平八郎元帥の軍服などを陳列したケースの前では非常に礼儀正しく、全員脱帽するという敬意を表し、特攻隊や沖縄のひめゆり部隊の遺品や遺書を感慨深く見ていた。帰り際に、ストレリー艦長は「厳粛な儀式に深い感銘を受けた」とその感想を語っている。
昭和三十九年十月七日には、練習艦隊で来日中のイタリア陸海空三軍の士官候補生九十名が、ジュリオ・アンドレオツテイ国防大臣、練習艦隊司令官ダラデーネ海軍中将とともに参拝している。この日、士官候補生たちは第二鳥居の前から軍楽隊を先頭に行進し、神職による修祓を受けた後、代表三名が花輪を捧げ、英霊の冥福を祈った。参拝後、一行は宝物遺品館で、人間魚雷回転特別攻撃隊遺品展などを約一時間にわたって参観。連合国艦隊を震撼させた特殊兵器「回天」については特に関心が高かったという。
ほかにも練習艦隊乗組員(士官候補生)による正式参拝があった国は、西ドイツ、タイ、アルゼンチン、チリ、スペイン、ペルーで、どのケースもみな軍服に身を包み、日本の作法(修祓など)に従って参拝している。
こうした練習艦隊による集団参拝以外にも、『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』の著者キングスレイ・ウォード氏(昭和六十三年十月二十七日)を始めとして学者、宗教家などアジア・アフリカ・南北アメリカ・オセアニア・ヨーロッパと地域や人種、宗教などの違いを超えて、実に幅広い分野の外国人が参拝している。
これもたとえ靖国神社が神道的な色彩を帯びようとも、日本における戦歿者追悼の中心的施設であることには変わりがないと見なしているがゆえであり、もし、靖国神社が軍国主義の亡霊を引きずっているということであるならば、こういった人々の参拝はあり得ないだろう。国際社会から見れば、誰がいかに言おうとも、靖国神社は日本における戦歿者追悼の中心的施設なのである。
▼ 靖国神社に寄せるビルマの熱き思い
とは言っても、靖国神社が幕末から大東亜戦争に至るまでの戦歿者を祀る施設である以上、特に大東亜戦争の評価と切り離して論じることができないのも事実である。その意味で、大東亜戦争で被害を蒙ったと主張する中国人や、欧米統治下における中間管理者としての地位を失った東南アジア諸国の一部華僑が今なお、大東亜戦争のシンボルとして靖国神社を非難するのはわからないでもない。
しかし、影がある時は必ず光もあるものだ。
「アジア=大東亜戦争の被害者」という構図だけでは、なぜアジアの要人たちが次々に靖国神社にそれも自主的に参拝するのかは理解できない。アジアには、中韓両国とは違った感情が存在するのである。
参拝記録を見ていると、昭和三十年代に入ると、大東亜戦争とその後の独立戦争を勝ち抜いて独立を達成したアジアの要人たちの参拝が増えてくる。特にビルマ(現ミャンマー)、インドネシア、タイの要人による参拝が目立つ。
正式に記帳していないので靖国神社の記録には残っていないが、この時期、ビルマのタキン・バセイン副首相は何度も来日し、そのたびに靖国神社に参拝している。ASEANセンターの中島慎三郎氏(福田首相の対アジア外交のスタッフ)によると、タキン・バセイン氏はある時、靖国神社の社頭で参拝し、涙を浮かべてこう語ったという。
「ビルマの独立のためにたくさんの日本兵が死にました。アジアが貧乏で弱いから、独立というビルマ自身の仕事を日本兵に頼みました。(インパール作戦では)二十万以上の日本兵が死去しました。いまもビルマの山野に眠っています。ビルマ人は兵隊さんに申し訳無いと思っています。ビルマ人は兵隊さんの志を忘れません。兵隊さんよ、ビルマを立派な国にするから見ていて下さい。兵隊さんが作ってくれたタイ・ビルマ(泰緬)鉄道は使っています。兵隊さん、ありがとう。」
ビルマは、独立運動の指導者として有名な「三十人の志士」が日本軍の鈴木敬司大佐(南機関)によって育てられた上、昭和十八年八月一日、日本軍の支援のもと独立を宣言した(国家代表バー・モウ)という経緯もあって、日本を抜きにしては独立を考えることはできない歴史を有する。特にインパール作戦は、侵攻してくるイギリス軍に対する防御作戦という色彩もあったため、ビルマの中には、日本軍がビルマ防御のために戦ってくれたと信じる人も多い。そうした経緯を踏まえれば、タキン・バセイン氏の発言も少しは理解できるのではないだろうか。残念ながら、日本が負けたため、ビルマはその独立を守るためにイギリスと提携せざるを得ず、ある程度イギリスの反日史観を受け入れたが、それでも国民は圧倒的に親日的であるという。
戦後、首相級として初めて靖国神社に参拝したのは、昭和三十一年四月十九日の中華民国立法院・張道藩院長(首相にあたる)だが、ビルマのウ・ヌー前首相も比較的早い時期に参拝に訪れている。東京で開かれた世界新聞編集者会議に来賓として出席したウー・ヌー前首相は昭和三十五年三月二十三日午後、靖国神社を訪れ、ビルマの民族衣装であるロンジー姿にガンバウンと呼ばれる帽子をかぶり、御本殿において敬虔な態度で黙祷を捧げた。戦時中、光機関の一員としてビルマ独立を支援し、戦後ビルマ政府顧問となった奥田重元氏はこう語っている。
《会議の余暇に都内を案内しようと申し出たが、いきなり靖国神社に参拝したいと言われたので驚いた。今回の訪日は世界新聞編集者会議で演説するためで国賓としてではないが、一国の首相が自発的に参拝したのはウ首相が初めてではないでしょうか、その点私たち戦友として感謝している。》
以後も、ビルマ政府要人による参拝は続き、記録が残っているだけでも、タンセン労働大臣とトン・シェイン駐日大使(昭和三十九年九月二十日)、ウ・バ・シーエ駐日大使(昭和四十四年三月二十七日)、ウー・ボー・レーサ農業大臣(昭和五十年十一月八日)、ウ・アエ文化大臣(平成七年八月二日)が正式に参拝している。
▼ アジア独立戦争としての大東亜戦争
インドネシアの政府関係者(軍人を含む)の参拝も多いのだが、インドネシアのケースを語るためには、まずその歴史に触れておく必要があるだろう。
三百五十年にわたってオランダに支配されたインドネシアはその間幾度となく、反オランダ独立闘争を起こしたが、そのたびにオランダの優秀な武器によって制圧されてしまうという苦い体験をもっている。それだけに、僅か七日間余りで宿敵オランダを打倒した日本軍に対する期待は熱狂的なものがあった。インドネシアの民衆の中には、これですぐに独立できると喜んだ者も少なくはなかったと言うが、日本軍としては巨大な欧米諸国と戦争中であり、すぐにインドネシアに独立を許すような余裕はなかった。日本の第十六軍司令官・今村均大将は、独立運動の指導者スカルノに対して、将来の独立に向けた準備を支援するかわりに戦争に協力するよう求めた。この取引にインドネシアの指導者は熟慮の末、応じた。そして日本軍に物資や労務を提供する代わりに、インドネシア人による軍隊(独立義勇軍=ペタ)の結成や官僚組織の確立、教育体制の整備などを日本軍の支援のもとに着々と進めたのである。
そして日本敗戦の二日後に独立を宣言し、再び植民地化を目論むイギリス、そしてオランダ軍と四年間にわたって激しい独立戦争を戦い抜いた。この独立戦争のために、日本軍はひそかに大量の武器や資金を提供しただけでなく、約千人(一説では二千人)の日本兵がインドネシアに残り、独立軍の一員としてオランダと戦ったと言われている。
昭和二十四年十二月、晴れて独立を勝ち取ったインドネシアではその後、膨れ上がった独立軍の要員を整理することになった。戦争の連続で困窮した政府の財政では、ろくに年金も支払えない。大多数の独立軍兵士たちは僅かばかりのお金と引き換えに退役を迫られることになった。
そうした辛い仕事を引き受けた復員軍人省長官のサンバス少将がある時、残留日本兵の部隊の解散を命ずることになった。一列に整列した兵士たちはみなインドネシア名をもち、日焼けした顔は長く続いたゲリラ戦の厳しさを物語るかのように険しさを増し、一見してインドネシア人と区別がつかなかったという。祖国を捨てて異国のインドネシアのために命をかけて戦ってくれた日本の兵士たち。そんな日本兵たちを僅かのお金で退役させなければならない。彼らのその後の生活保障もインドネシア政府はしてあげることもできない。サンバス少将は涙を流しながら一人一人に敬礼し、除隊を命じたという。
《今、インドネシアでもその他の国でも、大東亜戦争で日本の憲兵が弾圧したとか、労務者を酷使したとか言っているが、そんなことは小さなことだ。いかなる戦場でも起こり得るし、何千年前もそうだったし、今後もそうだ。日本軍がやったもっとも大きな貢献は、我々の独立心をかきたててくれたことだ。そして厳しい訓練を課したことは、オランダのできないことだ。日本人はインドネシア人と同じように苦労し、同じように汗を流し、“独立とは何か”を教えてくれた。これはいかに感謝しても感謝しすぎることはない。このことはペタの訓練を受けた者は、一様に感じていることだ。
特にインドネシアが感謝することは、戦争が終わってから日本軍人約千人が帰国せず、インドネシア国軍とともにオランダと戦い、独立に貢献してくれたことである。日本の戦死者は国軍墓地に祀り、功績を讃えて殊勲章を贈っているが、それだけですむものではない。》(名越二荒之助編『世界から見た大東亜戦争』)
日本人に対してこう繰り返し語ったサンバス少将が昭和五十年代のある時、ASEANセンターの中島慎三郎氏とともに靖国神社に参拝し、こう嘆いたという。
「あの世界を変えた大東亜戦争の英霊を祀る神社がなぜこんなに小さいのか。靖国神社は日本人だけのものではない。アメリカのアーリントン墓地ぐらいの大きさにすべきだ」
靖国神社は墓地ではなく、戦歿者の霊を祀っている場所なのであり、国立墓地のような広大な敷地を要することはない。その点でこの発言には靖国神社の性格に対する誤解が見受けられるが、その真意は理解できよう。「アジア諸国の独立を促した大東亜戦争の勇士たちを尊敬し、その英霊に敬意を払おうと思っているのは、何も日本人だけではない。大東亜戦争はわれわれアジアにとっての独立戦争だったのであり、その意味で、靖国神社はアジア独立の聖地でもあるのだから、それにふさわしい威容を備えてほしい」と、サンバス少将は訴えているのである。
▼ 大東亜戦争は日本人だけの戦いではなかった
こうした訴えがいまの日本人にとって奇異に聞こえるのは、日本人のほとんどが、そもそも大東亜戦争自体は日本人だけの戦いではなかったという事実をすっかり忘れ去ってしまっているからだ。当時日本人だった韓国、台湾、パラオの人々、同盟国だったタイ、フィリピン、ミャンマー、自由インド仮政府、中国の汪兆銘政権の人々が大東亜戦争をともに戦ってくれたという視点を抜きにしては、アジアの人々の靖国神社に寄せる思いは理解できない。
インドネシア独立戦争の指導者の一人ブン・トモ情報相は昭和三十二年、佐藤栄作首相にこう述べている。
《われわれアジア・アフリカの有色民族は、ヨーロッパ人にたいして何度となく独立戦争を試みたが、全部失敗した。インドネシアの場合は、三百五十年間も失敗が続いた。それなのに、日本軍が米・英・蘭・仏をわれわれの面前で徹底的に打ちのめしてくれた。われわれは白人の弱体と醜態ぶりをみて、アジア人全部が自信をもち、独立は近いと知った。一度持った自信は決して崩壊しない。日本が敗北したとき、“これからの独立戦争は自力で遂行しなければならない。独力でやれば五十年はかかる”と思っていたが、独立は意外にも早く勝ち取ることができた。
そもそも大東亜戦争はわれわれの戦争であり、われわれがやらねばならなかった。そして実はわれわれの力でやりたかった。それなのに日本にだけ担当させ、少ししかお手伝いできず、誠に申し訳なかった。》(ASEANセンター編『アジアに生きる大東亜戦争』)
敢えて言挙げはしないものの、心のどこかで「大東亜戦争はわれわれの戦争である」と思っているからこそ、いくら連合国や中国・韓国などが大東亜戦争を侵略戦争と非難し、靖国神社を軍国主義の中心と批判しても、そして当の日本の外務省が嫌な顔をしてもなお、アジアの要人たちは靖国神社に特別の思いを寄せ、自ら望んで靖国神社に参拝し続けてきたのではなかったのか。
▼ 国家存立の本質に関わるテーマとして
外交的な観点から靖国神社公式参拝を云々するのであるならば、靖国神社に熱い思いを抱き、戦後も靖国神社を訪れるアジアの要人が多数存在するという事実、そして少なくとも国際社会においては、「靖国神社は日本人の戦歿者追悼の中心的施設」と見なされていることを、私たちはまず素直に認めるところから考えていくべきである。
確かに大東亜戦争を侵略とみなす一部のアジアの人々が、靖国神社を「軍国主義のシンボル」と批判しているのは事実だ。しかし、「アジアの心情」を云々するのであるならば、日露戦争から大東亜戦争に至る我が国の歴史を評価するアジアの人々が、靖国神社をアジア独立の「聖地」と見ている事実を忘れては片手落ちであろう。
この相反する二つのアジアの心情のうち、現在の私たち日本人は、大東亜戦争を侵略とみなす一部アジアの心情だけを重視している。そうすることで、自覚しようとすまいと、実は靖国神社を戦没者追悼の中心的施設と見なす国際世論をも無視しているのである。
アメリカの国防総省(ペンタゴン)の中には、「靖国神社に参拝せず、自国の戦歿者に敬意も表さない日本の首相の言うことなど信用できない。本気で国を守ろうと思っているならば、戦歿者追悼を蔑ろにできるわけがない」という反発があり、だからこそ、日本はアメリカの同盟国として不適格だという意見も根強いという。在日米軍の司令官の多くが靖国神社に参拝していることを思えば、この指摘があながち的外れでないこともわかる。
現在、橋本首相率いる日本政府は、国防体制と日米同盟の強化という観点から日米ガイドラインの見直しとそれに伴う自衛隊法の改正を検討しているが、その一方で、早々に靖国神社の公式参拝の見送りを表明してしまっている。その表明が、日米同盟を実質的に担っているアメリカの軍事関係者、特に在日米軍時代に進んで靖国神社に参拝したアメリカの軍幹部たちにどのような影響をもたらすのか、一度でも考えたことがあるのだろうか。
恐らく、一国の首相たる者が「近隣諸国民への配慮」を理由に、祖国のために戦った自国の戦歿者を蔑ろにして憚らないという事実を知って、眉をひそめ、やがて何と情けない国だと侮蔑したに違いない。意味合いは違うが、靖国神社に参拝した多くのアジアの要人たちもまた、「なぜ日本人は靖国神社に参拝しないのか」「大東亜戦争をともに戦ったわれわれアジア人の心情をなぜ無視するのか」と怒り、やがて失望の思いを深めたに違いない。
現在、我が国の為政者たちは、靖国神社公式参拝を見送っても、一部の日本人から反発を買うぐらいだと高を括っている。戦後世代の関心も高いとは言えない。しかし国際的に見れば、一国の首相が靖国神社に参拝しないということは、「為政者たるものは自国の戦歿者に最大級の敬意を払うべきである」という国際常識に背を向けることであり、そうすることによって欧米諸国からもアジア諸国からも、侮りと不信感を持たれていることを知らねばならない。
靖国神社に鎮まる戦歿者は、世界の要人たちから敬意を払われることはあっても、自国の為政者たちから追悼の思いを捧げられることはない。こんな倒錯した事態を我が国はいつまで続けるつもりなのか。
欧米諸国やアジアの指導者たちがどのような思いで戦後、靖国神社に訪れ、参拝をしたのかを振り返っていけば、靖国神社が遺族など一部日本人のものだけではないことはわかるはずだ。靖国神社の問題は党利党略といった次元で扱うことのできない、国家存立の本質にかかわる重大なテーマであることについてもっと理解を深め、世界の要人たちがわざわざ参拝に訪れるにもかかわらず肝心の自国の為政者たちは参拝しようとしないこの異常な事態を、われわれ戦後世代の手によって改めたいものである。