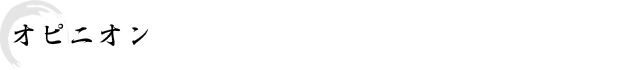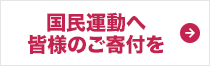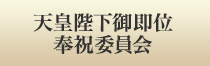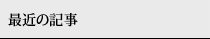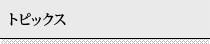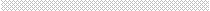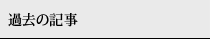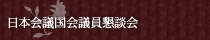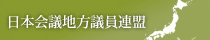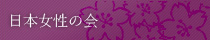日本は東京裁判史観により拘束されない
サンフランシスコ平和条約の正しい解釈
青山学院大学名誉教授 佐藤和男
一 平和条約第十一条についての誤解
大東亜戦争の終結直後に連合国占領軍によって強行されたいわゆる東京裁判(極東国際軍事裁判)が、国際法に違反する政治的茶番劇であったということは、近年においてすっかり日本国民の常識として定着した観があります。しかし、その反面、あくまでも東京裁判を肯定して、その判決中に示された日本悪玉史観を奉持し続けたいと考えている人々もいることは事実のようです。そのような人々は、えてして「日本は、サンフランシスコ平和条約十一条の中で東京裁判を受諾しているから、東京裁判史観を尊重する義務がある」と主張する傾向があるように見受けられます。最近では、政府部内にも同じような考え方で東京裁判史観に拘泥する人が若干いることが判明しています。しかし、平和条約十一条を右のように解釈することは、国際法理上、間違っています。その理由を以下に説明します。
まず問題の十一条の規定を次に掲げます。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」(外務省訳)
右の十一条の全文を読めば、本条の目的が、いわゆるA級およびB・C級戦争犯罪人を裁いた連合国側の軍事法廷が日本人被告に言渡した刑の執行を、日本政府に引受けさせるとともに、赦免・減刑・仮出獄の手続を定める点にあることが、明らかに理解されましょう。
これらの軍事法廷では、被告とされたのは個人で、国家ではなく、はっきりいえば、日本国家は軍事裁判には直接のかかわりを持ちません。その日本国家が連合国に代わって(国内の受刑者の)「刑を執行する」責任を負うなどするためには、「受諾」という行為が必要となるのです。
ところで、十一条の日本文では「裁判を受諾する」となっている点が問題です。サンフランシスコ対連合国平和条約(昭和二十六年九月八日調印、翌二十七年四月二十八日発効)は、日本語のほかに、等しく正文とされる英・仏・西語で書かれていますが、アメリカのダレス国務長官が原案を起草したという歴史的事実にかんがみ、まず英文の十一条から検討してみましょう。初めの部分は次のとおりです。
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
これで見ますと、日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文では accepts the judgments です。英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial,proceedings とは区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典 Black´s Law Dictionary の説明からも明白です。そこでは judgment は、The official and authentic decision of a court of justice upon the respective rights and claims of the parties to an action or suit therein litigated and submitted to its determination.(司法裁判所が、同法廷に提起されてその判定が求められている訴えないし訴訟の当事者の、それぞれの権利ならびに請求に関して下す、公式かつ有権的な決定)と説明されています。以上から、英語の本文では、問題の箇所は「判決を受諾する」意味であることが明瞭です。
次に、フランス語正文で同じ箇所を見てみましょう。
Le Japon accepte les jugements prononc s par le Tribunal Militaire International pour 1´Extr me-Orient et par les autres tribunaux alli s pour la r pression des crimes de guerre,au Japon et hors du Japon,et il appliquera aux ressortssants japonais incrarc r s au Japon les condamnations prononc es par lesdits tribunaux.
ここで注目されるのは、日本が、諸軍事法廷により「言渡された判決を受諾する」(accepte les jugements prononc s par……)と書かれていることです。フランス語では prononcer un jugement と使った場合、「判決」を下す(言渡す、宣告する)の意味であって、この場合 jugement は裁判を意味しません。
最後に、スペイン語正文で同じ箇所を見ることにします。
El Jap n acepta las sentencias del Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente y de otros Tribunales Aliados de Crimenes de Guerra,tanto dentro como fuera del Jap n,y ejecutar las sentencias pronunciadas por ellos contra nacionales japonesses encarcelados en el Jap n.
ここでは、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を受諾し、それらの法廷により言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれています。スペイン語の sentencia は、判決、または宣告された刑を意味しますが、裁判を意味する言葉ではありません。
以上、言語学的に説明しましたが、日本が平和条約十一条において受諾したのが「裁判」ではなく、「判決」であることが、おわかりいただけたことと思います。「裁判」と「判決」とでは、条文の意味が随分変わってきます。もともと英語正文の翻訳を基礎に書かれた日本語正文で、なぜ「判決」ではなく「裁判」の語が使われたのか、その理由と背景を探ることはある意味で重要ですが、ここではこれ以上深追いしないことにします。
二 講和条約とアムネスティ条項
国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、戦争が正式に終結するものとされます。つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、国際法上の戦争状態が終了するのです。日本の場合、昭和二十年九月二日に米艦ミズリー号上で連合国との間で「降伏文書」(連合国側の命名)の調印を行いましたが、この文書はポツダム宣言の内容を条約化して、日本の条件付終戦――日本政府が無条件降伏したというのは大きな間違いです――を正式に実現したもので、法的には「休戦協定」の性質を持ちます。
連合国占領軍は、日本が戦争終結の条件として受諾した事柄(ポツダム宣言六項~十三項に列記されています)を、日本に履行させるために、およそ七年間駐留して軍事占領行政を実施しますが、サンフランシスコ対連合国平和条約が発効する昭和二十七年四月二十八日までは、国際法的には日本と連合国の間に「戦争状態」が継続しており、いわゆるA級戦犯を裁いた東京裁判と、B・C級戦犯裁判とは、連合国が軍事行動(戦争行為)として遂行したものであることを、よく理解する必要があります。
日本国民の中には、大東亜戦争は昭和二十年八月十五日に終わったと思い込んでいる人が多いのですが、国際法の観点からいえばこれは間違いで、戦闘期間が終わっても軍事占領期間中は「戦争」は継続されていたと見るのが正しく、事実、連合国側は平和条約発効の時まで、戦争行為として軍事占領を行うという意識を堅持して、連合国の目的にかなった日本改造に力を注いだのです。
さて、ここで、アムネスティ条項(amnesty clause)の説明に移ります。前述のごとく戦争を終了させるものは講和ですが、第一次世界大戦以前の時代にあっては、交戦諸国は講和に際して、平和条約の中に「交戦法規違反者の責任を免除する規定」を設けるのが通例でした。これがアムネスティ条項と呼ばれるものですが、アムネスティとは「国際法上の大赦」を意味します。
国際法では伝統的に戦争それ自体は合法的制度とされ、戦争の手段・方法を規律する交戦法規に違反した者だけが戦争犯罪人として、戦時敵に捕らえられた場合に裁判にかけられて処罰されました。戦争を計画・遂行した指導者を犯罪人(いわゆるA級戦犯)とする国際法の規則は、厳密には今日でも存在していないと考えられています。(第二次世界大戦後、国際連合憲章の発効とともに、自衛戦争とは反対の侵攻戦争[俗訳・侵略戦争]は、明らかに違法行為とされましたが、重大な違法行為としての犯罪とは正式にはまだされておらず、このことは国際連合国際法委員会においても認められています。)
アムネスティ条項の説明の実例として、アメリカの国際法学者C・G・フェンウィック博士が自著『国際法』(一九三四年)の中で述べているものを要約しますと、同条項は「戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為をおかしたすべての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める」効果を持つものとされます。しかも、講和条約中に明示的規定としてアムネスティ条項が設けられていない場合でも、このような責任免除は講和(戦争終結)に伴う法的効果の一つであることが確認され、アムネスティ(大赦)が国際慣習法上の規則となっていることがわかります(五八二頁)。
国際法史上で有名なアムネスティ条項に、三十年戦争を終結させた一六四八年のウェストファリア平和条約の二条があります。そこでは、戦乱が始まって以来、言葉、記述、暴虐、暴行、敵対行動、毀損、失費のかたちで行われたすべてのものにつき、「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」と規定されています。このような「全面的忘却」(oubli general)――すべてを水に流すこと――の精神に基づくアムネスティ条項は、戦争を燃えたたせた国家間の憎悪の焔を鎮めるために必要とされ、ウェストファリア条約のほかにも、一六七八年のナイメーヘン条約、一七一三年のユトレヒト条約二条、一七四八年のエクスラシャペル条約二条、一七六三年のパリ条約二条など多くの講和条約中に見いだされます。
ナポレオン戦争後の一八一四年五月三十日にパリで調印された英仏間の平和友好条約は、十六条で次のように規定しています。「両締結国は、欧州を震動させた不和軋轢を完全な忘却の中に埋没させようと願望して、いかなる個人も、その地位や身分にかかわりなく、(中略)その行為、政治的意見、またはいずれかの締結国への帰属の故をもって、訴追されたり、権利を侵害されたり、あるいは虐待されたりすることがないと、宣言しかつ約束する。」
同様の趣旨の規定は、一八六六年八月二十三日にプラハで調印されたオーストリア-プロシャ間の平和条約の十条三項、一九一三年十一月十四日にアテネで調印されたギリシア-トルコ間の平和友好強化条約などに見られます。一九一八年三月三日にドイツ-ソ連条約の二十三~二十七条、一九一八年五月七日のドイツ-ルーマニア条約の三十一~三十三条約は、一般的アムネスティ条項を構成しています。(第二次世界大戦後にも、連合国側が結んだ対ハンガリー平和条約三条、対ブルガリア平和条約三条、対フィンランド平和条約七条に、「連合国の側に立って行われた行為」についてのアムネスティ規定が見られます。)
以上のような諸国の慣行を基礎にして、講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認されるのです。こうして、第二次大戦以前には、平和条約中にアムネスティ条項が置かれなくても、講和がもたらすアムネスティ効果には変わりがないとの考えが一般的で、戦争犯罪の責任を負う者も、平和条約中に特別の例外規定がない限り、講和成立後に責任を追及されることがないというのが、(第一次大戦後のドイツに関連して一時的に変則的事態が起こりかけたにもかかわらず)国際法学界の通説でありました。
三 平和条約十一条の機能
アムネスティ条項に関する以上の理解を前提とすれば、サンフランシスコ平和条約十一条の機能ないし役割は、おのずから明らかにされましょう。すなわち、十一条が置かれた目的は、この規定がない場合に、講和成立により独立権を回復した日本の政府が、国際慣習法に従って、戦犯裁判判決の失効を確認した上で、連合国側が戦犯として拘禁していた人々を――刑死者の場合はいたし方ないが――すべて釈放するかまたは釈放することを要求するだろうと予想して、そのような事態の生起を阻止することにあったのです。長い歴史を持つ国際法上の慣例に反した十一条の規定は、あくまでも自己の正義・合法の立場を独善的に顕示しようと欲した連合国側の根強い感情を反映したものと見られますが、平和条約草案を検討した昭和二十六年九月のサンフランシスコ会議では、連合国の間からも十一条に対し強力な反対論が噴出しました。
要するに、十一条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかったのです。日本政府は十一条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がありません。
筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない」と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。
外国の学者の中には、裁判官の人的構成が違っていたら、違った判決理由となる得る可能性を強調する人もいました。わが国の民事訴訟法一九九条一項は「確定判決ハ主文ニ包含スルモノニ限リ既判力ヲ有ス」と規定しています。既判力とは、裁判の内容としての具体的判断が以後の訴訟において裁判所や当事者を拘束し、これに反する判断や主張を許されない効力をいいます。右規定は文明諸国の「法の一般原則」を表していますが、この原則を重視する国際法学者もいたのです。もちろん、戦犯裁判なるものは普通の司法裁判とは異なり、本質的に国家の戦争行為(軍事行動)の具現であり、アメリカに即していえば、大統領により行使が決定される行政権(戦争遂行権)の延長戦上にあるものと考えられ、司法裁判と同じレベルでの議論は適当ではないのですが、判決文中の判決理由は既判力を持ち得ないとの原則の一種の類推適用は妥当でありましょう。
外国には「裁判官は判決理由を説明する義務を有しない」(Judices non tenentur exprimere causam sententias suae)という法諺すらあって、判決理由がさまざまであり得る可能性を認めて、重要なのは事件の決着であり、刑事裁判でいえば、刑の宣告が緊要であって、判決主文中に宣告された刑の執行により一件落着をはかることが急務であるとの考え方を含蓄しています。
対連合国平和条約の発効により国際法上の戦争状態を終結させて独立を回復した日本の政府は、東京裁判の判決理由中に示された歴史観ないし歴史的事実認定――歴史の偽造(パール博士の言葉)として悪名が高い――を盲目的に受けいれる義務を負わず、いかなる批判や再評価をもその裁判や判決理由に下すことが自由であり、この自由こそが、講和を通じ代償を払って獲得した国家の「独立」の実質的意味なのです。
戦後すでに五十年を経て、学界の研究成果は、東京裁判の判決理由中に示された史実とは異なる多くの真実(例えば、日本側共同謀議説の虚構性、判事・検事の立場にあったソ連こそ中立条約を侵犯した文字通りの侵略国であった事実など)を明らかにしています。戦前、戦中、日本国家の対外行動の中には政治的に賢明でないものがあったかも知れません。しかし、それをただちに実定国際法上の犯罪と誣しいることは許されません。近年わが国ではいわゆる“冤罪”事件について再審が行われ、あらためて無罪の判決が下される事例も少なくありませんが、上訴・再審の機会も与えられなかった復讐劇兼似エ而非セ裁判である東京裁判について、日本国民みずからの手で主体的再審を行って、日本民族にとり歴史の真実とは何であったのかを、先人ならびに児孫のために、明らかにしようではありませんか。
※初出 佐藤和男著『憲法九条・侵略戦争・東京裁判』(原書房、再訂版)
佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』(明成社)より転載