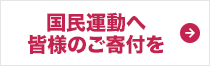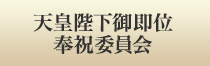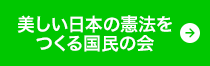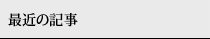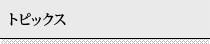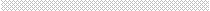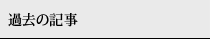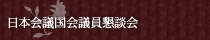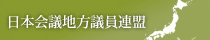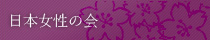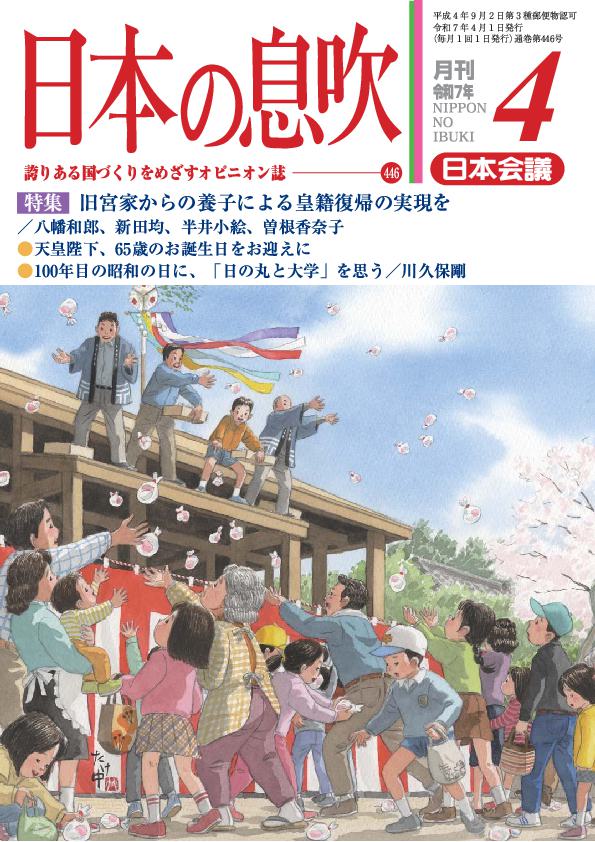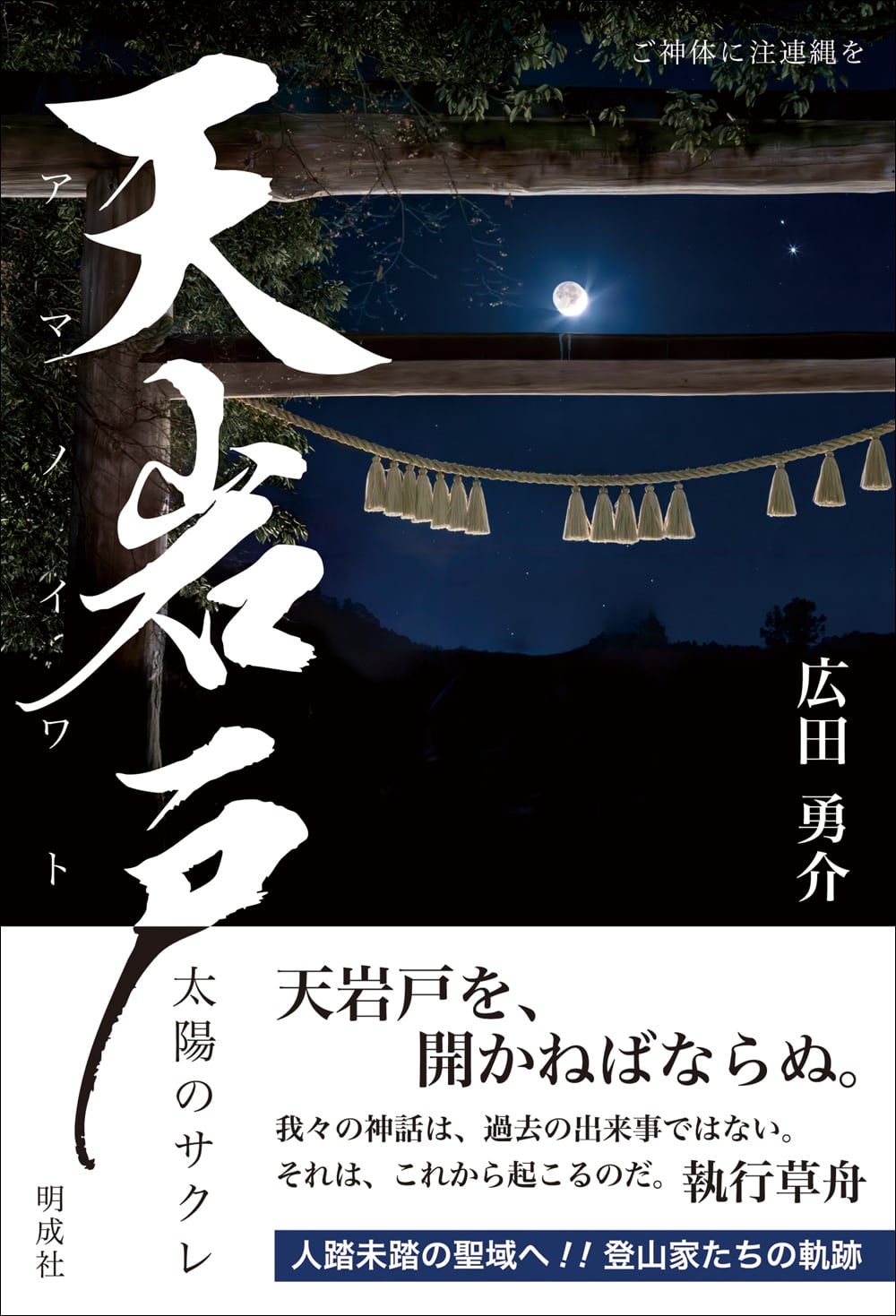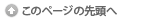[外国人参政権] 外国人地方参政権付与法案に反対する基本考え(日本会議)
①外国人地方参政権は明確に憲法違反
最高裁は、参政権につき平成7年に以下の判決を下しました。「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性格上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないと解するのが相当である」と。この判決では、外国人への参政権付与は、参政権を「国民固有の権利」であると規定した憲法に明確に違反していることになります。
②国防や国益にも重大な影響がもたらされる
靖国神社Q&A
Q1 靖国神社はどのような神社か?
近代日本の出発点となった明治維新の戦乱で、生命を捧げた人たちの霊を慰めるために、明治2(1869)年に明治天皇のご意志によって現在地(東京都千代田区九段)に創建された「東京招魂社」が起源。明治12(1879年)には「靖国神社」と社号が改められたが、「靖国」には「国の平和を願う」という明治天皇のお気持ちが込められている。本年(2001年)はご創健から132年目になる。 続きを読む…»
[新教育基本法] 日本の教育が大きく変わります
~新教育基本法の制定から学習指導要領、教科書検定制度まで、我が国の教育改革が大きく進んでいます
1、新教育基本法の制定
平成18年12月、国民待望の中59年ぶりに教育基本法が全面改正されました。私共は、全国各地における大会や街頭キャンペーンの推進、365万人の国会請願署名や37都道県420市区町村での地方議会決議などを促進し、その実現を図ってまいりました。改正された教育基本法には、道徳心、公共心、愛国心など日本人の心を育む教育目標が掲げられ、これにより混乱を続けてきた戦後教育を改革する大きな手掛かりが作られました。新教育基本法の主な特色をご紹介しましょう。 続きを読む…»
トピックス : 教育基本法,
奉祝 両陛下御成婚五十周年 作家:門田隆将さんに聞く
毅然たる日本人たれ!御成婚と学習院の奇跡
『神宮の奇跡』著者、作家 門田 隆将さんに聞く (※『日本の息吹』21年4月号より)
かどた りゅうしょう 昭和33年、高知県生まれ。中央大学法学部卒業後、出版社に勤務。政治、経済、司法、歴史、スポーツなど幅広いジャンルで活躍。平成20年、ジャーナリストとして独立。著書に『裁判官が日本を滅ぼす』『甲子園への遺言』(NHKドラマ「フルスイング」の原案)『なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の3300日』『ハンカチ王子と老エース』『激突!裁判員制度 井上薫vs門田隆将』など。
■戦後の経済発展の起爆年とも言える昭和三十三年に起こった二つの奇跡。学習院はなぜ、大学球界の最高峰リーグで優勝できたのか。皇太子妃決定の決め手は何だったのか。ベストセラー作家が描いた「御成婚」の真実とは― 続きを読む…»
私が歴史にこだわる理由 田母神俊雄・前航空幕僚長
このままでは自衛隊は戦えない!
田母神俊雄 前航空幕僚長 (※『日本の息吹』21年3月号より)
たもがみ としお 昭和23年福島県生まれ。防衛大学校(第15期)電気工学科卒業後、航空自衛隊に入隊。ナイキ(地対空ミサイル)部隊、航空幕僚監部厚生課長、南西航空混成団司令部幕僚長。第六航空団司令、航空幕僚監部装備部長、統合幕僚学校長、航空総隊司令官を経て、平成19年3月航空幕僚長、同20年11月定年退官。著書に『自らの身は顧みず』、共著に『日本は「侵略国家」ではない』がある。
●不可解な更迭劇
それにしても不思議だなあと思いますね。普通はどんな国の国民でも自国のことはいいと思いたいのに、「日本はいい国だ」と言ったら、「日本がいい国だとは何事だ。政府見解では日本は悪い国ということになっている」ということで、政府から首にされる。 続きを読む…»
天皇陛下御即位二十年を寿ぎて 明石元紹さんに聞く
忠恕(ちゅうじょ)の大御心
陛下の「ご学友」・元日産陸送(株)監査役 明石元紹 さんに聞く (※『日本の息吹』21年5月号より)
あかし もとつぐ 昭和9年1月、東京都生まれ。貴族院議員明石元長の長男、祖父は台湾総督・陸軍大将の明石元二郎。昭和13年より学習院高等科卒業まで皇太子殿下(今上陛下)の「ご学友」としてお側に。慶応義塾大学経済学部卒業後、プリンス自動車に入社。日産プリンス東京販売(株)取締役、日産陸送(株)監査役。その他、日本李登輝友の会・初代理事を務める。
天皇陛下御即位二十年に際し、各界からの声を寄せて頂きます。
●戦中、戦後の陛下
― ご学友となられた経緯は?
明石◆祖父の明石元二郎が男爵の爵位を頂戴したことがきっかけの一つです。 続きを読む…»
戦後政治の原点としての[東京裁判]批判
独立国家日本の「もう一つの戦後史」
終戦50周年国民委員会 ※佐藤和男・青山学院大学名誉教授監修『世界がさばく東京裁判』(明成社)「第6章」より転載。
「文明の裁き」と称して鳴り物入りで始められた東京裁判は実に2年6カ月もの時間を費やし、開廷423回、総計費27億円をかけて1948年(昭和23年)11月に判決を下した。我が国の指導者7人に絞首刑を宣告したこの判決は、これまでに紹介したように、弁護団ばかりでなく、少数意見を提出した判事たちや連合国の政治家たちからも厳しい批判を浴びた。
いくら国際法に基づいた公正な裁判だったと宣伝しても、真実は隠せない。「いかさまな法手続き」で行なわれた「政治権力の道具」に過ぎなかった東京裁判を強行したことで、GHQ(占領軍総司令部)及びアメリカ政府の権威は低下することとなった。判決が出された翌年の1949年(昭和24年)1月11日、アメリカのワシントン・ポスト紙は論説に次のように記した。 続きを読む…»
日本は東京裁判史観により拘束されない
サンフランシスコ平和条約の正しい解釈
青山学院大学名誉教授 佐藤和男
一 平和条約第十一条についての誤解
大東亜戦争の終結直後に連合国占領軍によって強行されたいわゆる東京裁判(極東国際軍事裁判)が、国際法に違反する政治的茶番劇であったということは、近年においてすっかり日本国民の常識として定着した観があります。しかし、その反面、あくまでも東京裁判を肯定して、その判決中に示された日本悪玉史観を奉持し続けたいと考えている人々もいることは事実のようです。そのような人々は、えてして「日本は、サンフランシスコ平和条約十一条の中で東京裁判を受諾しているから、東京裁判史観を尊重する義務がある」と主張する傾向があるように見受けられます。最近では、政府部内にも同じような考え方で東京裁判史観に拘泥する人が若干いることが判明しています。しかし、平和条約十一条を右のように解釈することは、国際法理上、間違っています。その理由を以下に説明します。 続きを読む…»
繰り返される拿捕事件と北方領土問題
『日本の息吹』平成20年2月号より
我が国固有の領土である北方領土がロシアに不法占拠されてより六十二年。未だ問題解決の兆しが見られないなか、平成十八年八月、ロシア国境警備隊により日本漁船が銃撃を受けて一人が死亡した。十九年十二月には四隻が拿捕され四人の船長は未だロシアに連行されたままである。 続きを読む…»
国境の島・対馬視察レポート「対馬が危ない」
●国境の島・対馬視察レポート「対馬が危ない」
日本会議地方議員連盟の対馬視察団先遣隊レポートを紹介。
(※『日本の息吹』20年10月号より)
日本会議地方議員連盟対馬視察団先遣隊
団長 小礒 明(こいそあきら)東京都議会議員
副団長 吉田康一郎 東京都議会議員
国境の島・対馬―福岡県から約一三〇キロ、韓国・釜山から約五〇キロに位置し、福岡よりも韓国に近い。我が国で六番目に大きいこの島が、今、韓国によって脅かされている。対馬で何が起きているのか。国境の島・対馬を守るため日本会議地方議員連盟の有志ら十五名が対馬の状況視察を行なった― 続きを読む…»
インドネシアにおけるオランダ350年と日本3年半の統治比較
●オランダ300年の統治
①強制栽培制度=19世紀、耕地面積の5分の1はコーヒー茶などオランダ向けの生産物を強制的に栽培させた。このため、多くの村が崩壊し、食料自給体制は解体、餓死者が続出し平均寿命は35歳にまで低下した。が、オランダが得た利益は実に国家予算の3分の1を占めた。例えば、ジャワ・マドゥラ地方の人口の半分に当たる400万人が強制栽培に従事させられる。 続きを読む…»
欧米列強のアジア侵略はいかにして行われたか
15世紀の大航海時代で世界に進出した西欧列強は、やがてアジア全域を植民地化した。彼ら白人帝国主義国はいかなる侵略行為を行ったのか-。
1 掠奪と搾取
350 年にわたりインドネシアの香辛料など独占的に収奪したオランダは、19世紀に入ると、強制的栽培制度を導入し耕地の5分の1(実際は半分)にわたって、コーヒー・砂糖・藍などのヨーロッパ市場向け作物を強制栽培させた。これによる巨額な収益は国家予算の3分の1を占めた。 続きを読む…»
世界はどのように大東亜戦争を評価しているか
自存自衛と大東亜の解放を掲げて戦われた日本の戦争は、アジアの諸国民や各国の識者からどのように受け止められているのだろうか-。
■イギリス
◎アーノルド・J・トインビー 歴史学者
「第2次大戦において、日本人は日本のためというよりも、むしろ戦争によって利益を得た国々のために、偉大なる歴史を残したといわねばならない。 続きを読む…»
学校行事としての靖国神社・護国神社訪問が解禁へ
①衛藤晟一議員の質問に対して、渡海文科大臣が、訪問を禁止した「昭和24年通達」の該当箇所の「失効」を明言
②平沼赳夫議員の質問主意書に対して、「学校行事の一環として靖国神社等を訪問してよい」と閣議決定
驚くべきことに、「学校が主催して、靖国神社、護国神社(以前に護国神社あるいは招魂社であつたものを含む)および主として戦没者を祭った神社を訪問してはならない。」――この一節によって戦後、学校行事としての靖国神社・護国神社訪問が禁止されてきました。
問題の一節は、昭和20年にGHQが出した「神道指令」を受ける形で昭和24年10月25日に出された「社会科その他、初等および中等教育における宗教の取扱について」の一節です。 続きを読む…»
皇室制度の抜本的見直しを目指して
大原康男 國學院大学教授
(※『日本の息吹』19年2月号より)
秋篠宮悠仁親王のご誕生によって、小泉純一郎前首相の下で性急に進められようとしていた皇室典範の改定はひとまず白紙撤回となったことは歓迎すべきであるが、だからといって、しばらくは皇室典範に関する議論を凍結してはどうかという声には賛成できるものではない。いや、今回の論議を契機として一般国民の間に俄[にわ]かに高まってきた皇室典範への関心が薄れないうちに、単に皇位継承問題だけでなく、戦後六十年の長きにわたって放置されてきた皇室制度の諸問題を抜本的に見直す機会となってほしい。 続きを読む…»